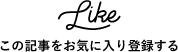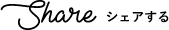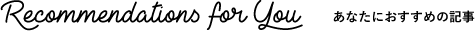【食養レシピ】梅雨時の体の湿気払いを。切干し大根の超簡単はりはり漬け&養生スープ。

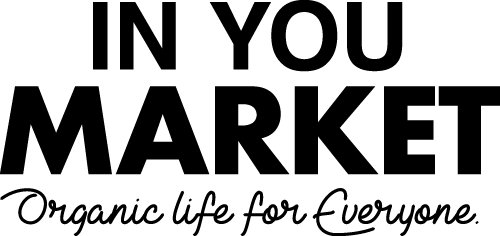
本物のオーガニックが見つかるオーガニックショップ
日本人は四季とともに暮らしています。
春から夏にかけては、冬場に溜めこんだ老廃物をデトックスし、新陳代謝を高める「排出」の季節。
免疫力の低下する秋から冬にかけては、体を温めて栄養を蓄え、抵抗力のある体をつくる「補給」の季節。
そして、この梅雨の時期は、「水毒」といって体の中に余分な水分を溜めこみやすくなる季節。
体に老廃物が停滞しがちになります。
じめじめした湿度と低気圧が重なり、体がだるく重く、むくみや頭痛なども起きやすい季節です。
この時期になると便秘や下痢を繰り返したり、上半身は暑いのに下腹や足元がひんやりする方も多いのでは?
これらの症状も東洋医学では「水毒」と呼ばれ、体の水分のめぐりが滞ることで起こるとされます。
人間の体の70%以上は「水」で出来ています。
そして余分に溜まった水には、毒素や老廃物が滞ります。
体に湿気がこもる梅雨は、体内の停滞した水分を流して水のめぐりを良くし、ゆるんだ体を引き締めたい季節。
この時期に必要な食養生をご紹介します。
【1、カリウムの多い食材を摂る】

枝豆・納豆・切干し大根・ほうれん草・アスパラ・すいか・きゅうり・パセリ・ひじき・昆布・アボカド・アーモンドなど、
カリウムを多く含む食材を取り入れることで、体内の余分な水分を老廃物とともに排出する。
体の中をお掃除する役割があります。
ただし、カリウムを摂りすぎると体内のミネラルバランスが崩れて体を冷やしてしまうので、
必ずミネラル豊富な塩分(ナトリウム)をプラスし、カリウムとナトリウムのバランスを整えましょう。
昔から、
スイカやトマトには塩。
枝豆は天日塩で釜茹で。
きゅうりや茄子は漬物に。
豆腐や冬瓜は味噌汁に。
といったふうに。
美味しく食べる知恵は、体を冷やさないようにする生活の知恵なのですね。
【2、クエン酸の多い食材を摂る】

お酢・梅干・柑橘類など、クエン酸の多い食材を料理にとり入れ、疲労を回復。
胃腸の働きも活発にしてくれます。
特に夏場は「酢の物」や「梅肉和え」や「マリネ」などが最適。
クエン酸回路はビタミンCと一緒に摂らないと働かないので、
ビタミンCの多い夏野菜をお酢や梅肉などと一緒に合わせることで吸収率がグンとアップします。
 出典 http://www.misbit.com/recipe
出典 http://www.misbit.com/recipe
ビタミンCの爆弾と言われる「ローズヒップ」には、クエン酸の豊富な「ハイビスカス」が必ずセットになった
「ハイビスカス&ローズヒップティー」があります。
これも生活の知恵ですね。
 出典 faura.jp
出典 faura.jp【3、薬味を活用する】
 出典 tabelog.com
出典 tabelog.com夏野菜や冷たい麺類などで体が陰性に傾きがちなこの時期の献立には、
ねぎや生姜など薬味を添えることで代謝を上げ、体を冷やしすぎないようにします。
薬味はまさに「薬」。
少量でも食事に添えることで、様々な薬効を得られます。
特に香りの強いネギ、生姜、にんにく、みょうが、大根おろし、大葉、バジル、パクチーなどには、
血の巡りをよくしたり、体に溜まった毒素を解毒する作用もあるので、旬の時期にはたっぷり楽しみたいですね。
【4、夏場は玄米より白米や分づき米に。】
 出典 asagohan.santoku-net
出典 asagohan.santoku-net体に余分な熱が溜まりがちな梅雨から夏にかけては、陽性の力が強い玄米より、
白米や分づき米(もしくは押し麦や雑穀入りの白米)のほうが体を整えてくれます。
また、夏場は胃腸の機能が低下して食欲が落ちる時期なので、
玄米だとますます胃腸に負担をかけてしまい、夏バテを起こす原因に。
季節によってお米の食べ方も自然と変わってくるものなので、
健康効果を重視するのではなく、なるべく自分の体の声を意識してみましょう。
「○○がよいと聞いたから毎日食べなきゃ」
「毎日○○を食べる習慣にしなきゃ」
なんて、食べ物を「知識ありき」で食べていませんか?
食べ物は、脳みそで食べるのではなく、体で食べるものです。
健康情報や話題の食材よりも、ずっとずっと自分の健康のことを考えてくれているのは、「自分の体」です。
寒い季節は無性に玄米や味噌汁が飲みたくなる、
疲れている時はすっぱいものが食べたくなる、
調子のいい日はしっかりお肉を食べたくなるし、
玄米を受けつけない日もあれば、果物を欲する日もある、
便秘の時は食欲がなくなるし、
風邪をひいた日は、何も食べたくなくなる。
そうやって、体は常に自分を「整えよう、整えよう」としています。
胃薬を飲んでまで食事したり、無理してスーパーフードなど食べたいと思わないはずです。
健康の効果ばかりに気をとられると、肝心の体のサインを聞き逃してしまい、
本来備わっている「自己治癒力」を鈍らせてしまうことになりかねません。
「今日の自分の体調は、何を欲しているのか。」
体のサインは、どんな健康情報にも勝るもの。
そしてそのサインは季節の移り変わりとともに変化していくものです。
旬のものを食べる。
楽しんで食べる。
四季に沿った暮らしをする。
これが何よりの養生になるわけですね。
戻し汁にも栄養価がたっぷり!体の湿気払いをして、ゆるんだ体を引き締める乾物活用レシピ

さて、それでは低気圧な体を乗り切りるレシピ。
ごはんが止まらなくなるくらい美味しい「切干し大根のナムル風はりはり漬け」と、
その戻し汁で作る「オニグラ風スープ」です。
かつて武士の強靭な肉体や、お百姓さんたちの丈夫な足腰を作ったのは、
牛乳やチーズやプロテインではなく、
味噌、米、そして乾物。
切り干し大根に、高野豆腐、海苔、昆布、ごま、ひじき、豆、干し椎茸に干し野菜に、鰹節。
どれもビタミン・ミネラル・アミノ酸が凝縮しています。
日本人になくてはならない存在、乾物。
まさに日本のスーパーフードなのです。
[amazonjs asin=”B008V82K1U” locale=”JP” title=”有機栽培 国内産天日干し 切り干し大根 30g”]
切り干し大根のカルシウムは牛乳の2倍!
鉄分も亜鉛もお肉なみの含有量です!
豊富なカリウムと食物繊維が体に滞った老廃物を排出する、デトックス食材の代表格。
古くから切干し大根は、
「にきび・吹き出物・肌荒れ」
「フケ・抜け毛」
「むくみ・手足の冷え」
に薬効があるとして重宝されています。
特に、切干し大根の戻し汁は、とっても優秀!
なんせ、これらの栄養がぎっしり戻し汁に移っているんですから。
捨てないでくださいね!
戻し汁は、と〜〜っても甘くて美味しい「だし汁」として使えるのです。
味噌汁やスープや煮物のだしにもなるし、
ブイヨン代わりにカレーに加えるのもおすすめ!
カラメルのような風味があるので、カレーがとってもコク深い仕上がりになります。
コンソメなど余計な調味料が必要なくなりますよ。

【煮物より簡単!体の湿気払いをする 切干し大根のナムル風はりはり漬け】

仕込んで1時間で食べられる即席漬けです。
ごま油を加えると、これだけでご飯もお酒もすすむぐらいウマウマな甘酢漬けになりますよ。
【材料】
・切干し大根 1袋(30g)
・にんじんのせん切り(あれば) 1/3本分
・昆布 5cm
・ごま油 小さじ2
・好みでいりごま 小さじ2
・鷹の爪 1本(種を除く)
・醤油 大さじ1
・お酢 大さじ1
・みりん 大さじ1
・きび砂糖(またはメープルシロップ)大さじ半分
※具材の量によって調味料は増やしてください。全体に調味料がいき渡ればOKです。
【作り方】
1、切干し大根と昆布をたっぷりの水で戻し、水気をしぼる。昆布は戻したら千切りに。 2、ビニール袋(ポリエチレン系)に、ごま油といりごま以外の材料をすべて入れ、もみもみする。
2、ビニール袋(ポリエチレン系)に、ごま油といりごま以外の材料をすべて入れ、もみもみする。※ビニール袋はプラスチック製のものではなく、ポリエチレン製のシャカシャカしたタイプのものが安心です。
 3、もみもみし終わったら、鷹の爪を加えて空気を抜き、常温に1時間おく。
3、もみもみし終わったら、鷹の爪を加えて空気を抜き、常温に1時間おく。出来上がりにごま油といりごまを混ぜて、保存容器に入れる。冷蔵で1週間保存可能。

【コンソメいらず。体のめぐりを良くする、切干し大根のオニオンスープ】

この一杯で貧血予防、吹き出物、肌荒れ、抜け毛、むくみ、冷え予防、お通じの改善と、
女性のすべての悩みを改善してくれる、まさに養生スープ。
【材料】
・切干し大根と昆布の戻し汁 2カップ(戻し汁が足りない場合は水を足して2カップにする。)
・玉ねぎ 1/2個
・自然塩 3つまみ〜(味をみて調整)
・醤油 小さじ1〜2
・カレー粉 少々
・黒胡椒 少々
・オリーブオイル 大さじ1
【作り方】
1、玉ねぎをみじん切り(または薄切り)にし、塩とオリーブオイルであめ色になるまで炒める。2、カレー粉を加えて玉ねぎになじませたら、切干し大根の戻し汁を一気に加え、ひと煮立ちさせる。
3、醤油・塩・黒こしょうで味をととのえて出来上がり。
夏までもう少し。
体内の水のめぐりをよくして、気持ちよい汗がかけるようにするために、今のうちに体を整えておきましょう。
なぜなら「汗をかく」というのは、毛穴からの最大のデトックスだからです。
夏までに代謝を上げて、たっぷり汗をかけるように、乾物の力、活用しましょう。
梅雨時期に不満のない毎日をサポートしてくれるこちらの商品もおすすめ
この記事を読んだ方へおすすめしたい他の記事
卵不使用!口どけなめらか簡単マクロビオティック豆乳マヨネーズの作り方。
【食養レシピ】5分でタンパク質たっぷりおつまみ、高野豆腐のバルサミコステーキ。
はじめてでも簡単! 無添加、白砂糖を使わない、らっきょう甘酢漬けレシピ&漬け酢活用術10選
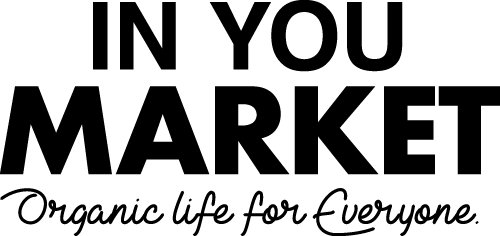
本物のオーガニックが見つかるオーガニックショップ

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)