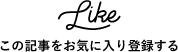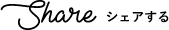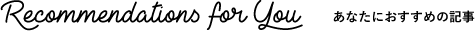お砂糖なしでこの甘さ!素材の甘さを堪能できるノンシュガー・にんじんジャムの作り方。

さて、前回のノンシュガー・アップルパイに引き続き、
今回はお砂糖なしで作る「にんじんりんごジャム」を紹介します。
お砂糖なしでもこの甘さ!
きび砂糖も甜菜糖もメープルシロップも羅漢果も甘酒も、甘味料は一切必要ありません。
冬に最も必要なビタミンAと、デトックス成分のペクチンがぎゅぎゅ〜っと詰まったジャムです!

ビンに詰めて贈り物に差しあげたら、
きっと驚くはずです。
「本当にノンシュガーなの???」
はい、ノンシュガーです。
ジャムを砂糖なしで作るにはちょっとしたコツがあります。
そのひとつが「塩」です。
少しのコツさえ分かれば砂糖を使わなくても素材の甘さを最大限に引き出し、
濃縮させることができます。

お砂糖不使用、素材そのままの栄養がをギュッと詰まっているので、
パンやスコーンやクラッカーにたっぷりぬって食べられますね。

子供や妊婦さんにはこのくらいの「野菜のショ糖だけの甘み」が最も丁度いい甘さだと思っています。
大人はこれを機会に、素材の味を感じられるように自分の舌をリセットしてみるのもいいでしょう。
もし「もう少し甘みが欲しい」という場合は、
メープルシロップやアガベシロップなどお好みの甘さを足してください。
自分好みの甘さに変えられるのも手作りだからこそ出来る安心感ですね。
温めることで倍増するにんじん・りんごの免疫力アップ成分。

最強の抗酸化ジュースといわれる「にんじん・りんごジュース」、飲まれている方も多いと思います。
ただ、冬になると冷えますから、ジュースやスムージー自体を体が欲しなくなる方も多いのでは?
むしろそれが体の自然な反応です。
スープや味噌汁、煮物、シチュー、ジャムなど、
寒い時期には寒い時期の「陽性の調理法」があり、陽性のビタミンの摂り方があります。
季節が変わっても、サラダやスムージーなど「陰性の強い調理法」を続けていたら
体調を崩す原因になりかねません。
冬に必要なのはにんじんの「ビタミンA」。
ビタミンAは皮膚の粘膜を丈夫にし、
乾燥や紫外線やウィルスに強い体を作る「最強のウィルスブロッカー」です。
そしてもうひとつ必要なのは、にんじん・りんごを「温める」ことによって生まれる毒素排出成分「ペクチン」と、整腸作用の「オリゴ糖」。

ペクチンは腸内の有害物質を吸着し、体外へ排出してくれるデトックス成分。
特にりんごは加熱することでペクチンが生の9倍に変化し、オリゴ糖も2倍以上に増えます。
ペクチンの作用で老廃物をお掃除し、キレイになった後の腸内に必要なのは、
善玉菌のエサになるオリゴ糖。
(ちなみにオリゴ糖は汚れた腸内環境の中では悪玉菌のエサになってしまいます!)
加熱したにんじん・りんごには、
毒素排出コンビ「ペクチンとオリゴ糖」が豊富なだけでなく、
免疫力を高めるビタミンAやβカロチンも凝縮。
生やジュースで摂るよりも吸収のよい状態で摂ることができるんです。
マクロビオティックのおやつでよく登場する
焼きリンゴや、りんごの葛煮、にんじんのポタージュなども、
お腹の調子を整えて、オリゴ糖の吸収を高めてくれます。

つまり、
生には生の、
加熱には加熱の良いところがあるということ。
一方で、生のりんご・にんじんには酵素が豊富ですから、
自分の体調によって「生か、加熱か」をチョイスするといいですよね。
「今日は無性に生のリンゴをかぶりつきたい」とか、
「今日は温かい焼きリンゴでお腹の調子を整えたい」
とか。
体の声は正直なので、その時食べたいものが、体が必要としている栄養素だと思います。

このジャム作りには
畑の味が濃い自然栽培のにんじんを使うと、ほんとうに、ほんとうに美味しいです!!
冬の栄養がギュッと詰まったノンシュガー・にんじんりんごジャム。

【材料】
・にんじん 2本
・りんご 大1個
・自然塩 小さじ1/3弱
・レモン汁 大さじ1
・エキストラバージンオリーブオイル大さじ2〜3
・バニラオイル(またはバニラエクストラクト) 少々
※しっかりした甘みが欲しいという場合は、メープルシロップやアガベシロップなど好みの甘さを足してください。
[amazonjs asin=”B0040QC2CY” locale=”JP” title=”ドーバー モンレニオン 100%天然濃縮ヴァニラ原液 23g”]
このレシピに使用したオリーブオイル

最高級ギリシャ産エクストラバージンオリーブオイルを購入今すぐここをクリック!
オイルの質にもこだわりたいところ。
【作り方】
1、鍋に薄切りにしたりんごとにんじんを入れ、塩をまんべんなくまぶす。(両手で返すようにしながら塩が全体に行き渡るように。)
2、レモン汁をふり、そのまま10分ほどしばらく置いて、リンゴから水分を引き出す。

3、鍋を中火にかけ、煮立ったら火を弱めてフタをし、全体がくったりと柔らかくなるまで蒸し煮にする。
りんごから出る水が多い場合は、最後に火を強めて煮詰め、水分をとばす。
4、あら熱がとれたらオリーブオイル、バニラオイルと一緒にフープロにかけて、
なめらかなペースト状にする。

5、煮沸消毒したビンにつめて、空気を抜くようにトントンと落とし、フタをして冷蔵保存する。
冷蔵で2週間、冷凍で1ヶ月保存可能。

美味しく食べるコツは、体に栄養素を吸収させるコツでもある。

このジャムの「美味しさのポイント」は、最後に加える油脂。
にんじんのβカロチンは脂溶性なので、
油脂と一緒にとることで体への吸収率が格段に上がります。
(つまり生でにんじんをかじってもビタミンは野菜の固い細胞壁で守られており、ほとんど腸に吸収されないのです。)
ジャムに限らずにんじんを食べるときは
ごま油できんぴらにしたり、
オリーブオイルや亜麻仁油と混ぜてにんじんドレッシングにしたり、
グラッセにしたり、
βカロチンには油を組み合わせることを意識してみると良いですよ。
脂溶性のカロチンを持つ野菜は他にも
カボチャ、ほうれん草、小松菜、パプリカ、ブロッコッリー、アスパラなどなど。
これらのカロチンは油脂と一緒に摂ることで吸収されます。
カボチャなら油を使ってグラタンやポタージュスープにしたり、

小松菜やほうれん草、ブロッコリーは、ごまの油脂と合わせて「ごま和え」や「ナムル」にしたり、
パプリカやアスパラはオリーブオイルでサッと炒めたり。
おいしく調理することで、体への吸収がグンとアップするわけですね。
試してみなくちゃはじまらない。
まずはオーガニックのにんじんとりんご、買ってみる?
この記事を読んだ人におすすめのほかの記事
オーガニックりんごで作る、ノンシュガー・グルテンフリー「ふんわり玄米白玉団子と りんごぜんざい」のレシピノンシュガーでも大満足。りんごの甘味だけでつくる「あんこ」と「おしるこ」の作り方。
パンに塗っても豆乳に混ぜて飲んでもOK!甘味料不使用。材料3つで、超簡単りんごクリームの作り方
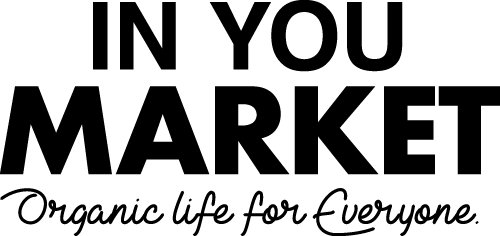
本物のオーガニックが見つかるオーガニックショップ

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)