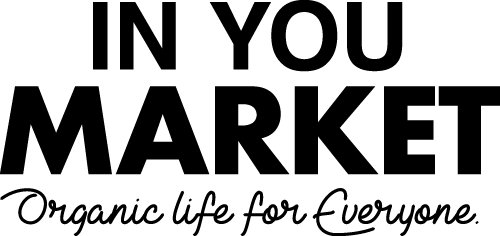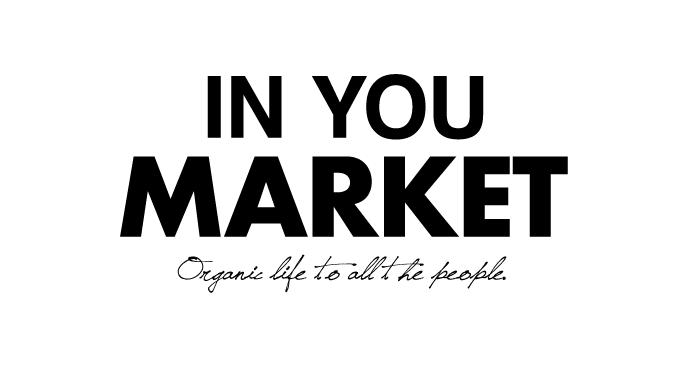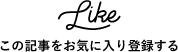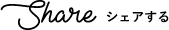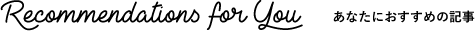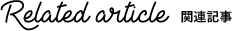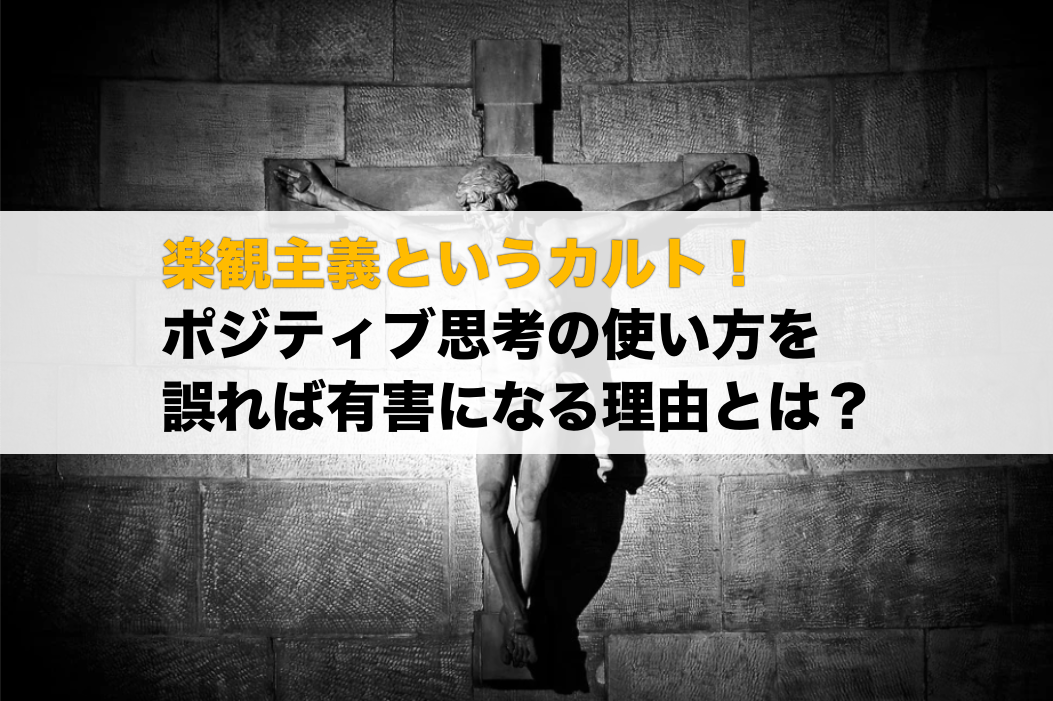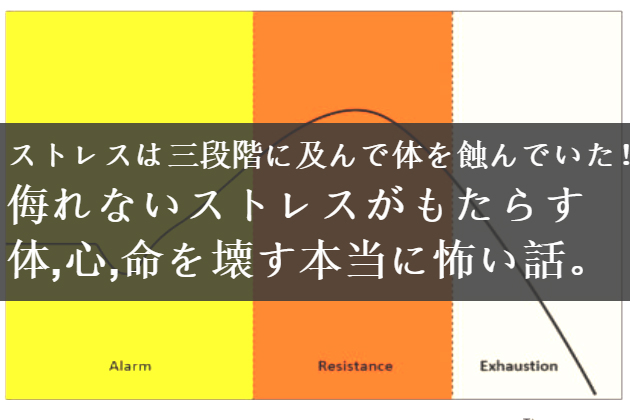晴れ 時々 農業 〜 私の「援農」日誌 vol.1:2020年7月号

晴れ 時々 農業 〜
私の「援農」日誌 vol.1: 2020年7月号
今年の梅雨はことさら雨量が多いみたい。雨の合間を縫って、私が週一回、「援農」のために通うのは、
有機農業が盛んな千葉県南部の山間地。
緑がだいぶ濃くなった田んぼ、勢いよく育つ夏野菜の畑に、
新芽がかわいい落花生や黒ゴマの畑・・・。
そう、田や畑は、私の大切な職場のひとつです。
「農」を「援(たす)」ける、と書いて「援農」

時間を少しさかのぼって、
2011年に東日本を襲った大震災は、
千葉県のベッドタウンで暮らしていた私に、
大きな衝撃を与えました。
3人の子どもを妊娠し、出産する過程で、
ただ何となく、自然寄りには生きてきたけれど。
長女の喘息が悪化したのを機に、千葉県南部に小さな家を借り、
週末に子ども達を連れて通った一年間。
自然豊かで、温和な人々に囲まれた海辺での日々は、
時間にしたらほんの僅かだったけれど、
ここで生きていこう、と私に決意させるには充分でした。
そして、この移住に遅れること一年。
今年、私の援農生活は七年目を迎えました。
「援農」って、農業に馴染みのない方には、
耳慣れない言葉かもしれません。
また、農業をよく知る方からも
「アルバイト?それとも新規就農を目指して研修中?」と聞かれることも。
農家に労働力を提供し、その対価として農作物を分けていただく。
援農をシンプルに捉えれば、こういうことになります。
でも、それだけではない、もっと大きなものがそこにはあって。
それが、私が援農を続ける理由です。
農との最初の出会いは娘の「森のようちえん」で。
〜鴨川の大山千枚田から、旧三芳村のY農園へ

▲千葉県南部にある旧三芳村は、有機農業発祥の地ともいわれている
実をいえば、援農という言葉を、私自身が知ったのはつい最近のこと。
農業ド素人の私が、無理することなく続けている、この農作業のお手伝いを、
言葉に当てはめてみたら、どうやら援農というらしい。
そんな私が農業に初めて触れたのは、長女の幼稚園時代でした。
農作業って愉しい!!
〜「森のようちえん」でかじった農の悦び

▲「森のようちえん」では、五感を使って子供の心身を育む
今年、小学校高学年になった長女が三年間(2013年〜2015年)通った幼稚園は、
千葉県南部に拠点を置く、いわゆる「森のようちえん」。
園舎を持たず、屋外保育を主な活動内容とする、
「森のようちえん」は、いまや全国区になりつつあります。
自然豊かな公園を、おにぎりと着替え、雨合羽が入ったリュックサックを背負って、
保育スタッフやお当番の母親とお散歩するのが、子どもたちの日課。
その活動に月一ペースで、田畑で農作業をする「田畑の日」が入ります。
この日は母親たちも自由に参加可能。
初めは、親離れできない長女の様子が気になって参加していた「田畑の日」。
なのに結局、田んぼも畑も、私の方が夢中になっていたりして。
もち米、ソラマメ、ジャガイモ、サツマイモ…
収穫量は決して多くなかったけれど、泥や土に触れながらの農作業の過程や、
そこでしか出会えない動植物がとても愛しかった。
もともと自然観察が大好きな私。
都内を歩いていても街路樹や植込みなどの植栽が、つい気になってしまうくらい。
それも、私が農業に大きな魅力を感じた、理由のひとつかもしれません。
援農デビューは鴨川の棚田で。
〜絶品ランチと感謝の言葉をいただいて、ますます援農に傾倒

▲日本の棚田百選にも選ばれている千葉県鴨川市の
「大山千枚田(おおやませんまいだ)」。
江戸時代から良質な米として知られる「長狭(ながさ)米」の産地だ
ところで、日本人の主食であるお米のことって、皆さんは、どれくらい知っていますか?
毎日食べているのに、意外と何も知らない。学校では何も教えてくれなかった。
その事実に私が気づいたのも、長女の「森のようちえん」時代でした。
田植えや草取りもをしたけれど、その前って田んぼはどうなっていたの?
そもそも稲の種ってお米なの?
刈り取りまで、稲はどう成長していくの?
有機農法とそうでない農法との違いは?
自分の無知を埋めようと、いてもたってもいられなくなって、
同じ幼稚園に子供を通わせていた鴨川在住の友人夫妻にお手伝いを申し出たのです。
友人夫妻はその当時、県内の米どころとして知られる棚田「大山千枚田(おおやませんまいだ)」で、
小規模な米作りとカフェの運営を行っていました。
こじんまりした田んぼなら、その全体像を見ることができそうとか、
当時は私と同じく素人に近かった友人夫妻に、勝手に親近感を覚えたことも
お手伝いをするモチベーションのひとつでしたが、
本当のところは、ご主人がつくる南インドカレーと奥さんが焼くパンが
最高に美味しかったから。
そんな、農作業の後にご馳走になるランチと稲刈り後にいただいた感謝の言葉、
そして3キロのお米のずっしりとした重み。
これで私は、援農にすっかりハマってしまったのです。
Y農園のこと
〜農業とは尽きない学び。
そこには同時に健やかな人間関係もあった

▲穏やかに草を食(は)むヤギの姿に癒される
お米も野菜も、ほとんどの農作物の栽培が一年に一回の真剣勝負です。
雨量や日照時間、台風、気温など、農業に大きな影響を与える気象条件は毎年異なります。
豊作も凶作も全て受け止めて、その上で来年の対策まで立てなければならない。
気力や体力はもちろん、少しの変化にも気づくことができる細やかな観察眼に、
常に先を見通す力も農業には必要です。
さらに、誤りを認められる素直な心と、改善策を講じる臨機応変な姿勢。
そして、よりよい作物を追い求める知識欲と強い意志。
対・農作物だけでなく、その先の販売に繋がる消費者との関係や、
農業を守るための後継者の育成、はたまた地域の人たちとの関係作りも重要です。
農業は周囲の人の暮らしと地続きで行われるため、対人面においても、
農作物に対するのと同じような気遣いを要するのです。
そして、それを軽やかに、愉しげに体現・実行しているのが、
私が現在、鴨川の棚田に続いて、援農でお世話になっている、
旧三芳村(現南房総市)にあるY農園のご夫妻です。
米、小麦、大豆、ゴマ、野菜…
自分たちが食べたいものだけを育てていった結果が、
Y農園のご夫妻の暮らし

▲実は繊細で育てるのが難しい、夏野菜の代表格・ナス
農繁期だけではなく、一年を通じて田んぼや畑を見てみたい。
農業への好奇心が尽きない私は、長女の卒園と同時に、
「森のようちえん」の「田畑の日」でお世話になっていたY農園に、
週二回の援農を申し入れることになりました。
15年ほど前に新規就農したY農園のご夫妻は、食べもの全般や、
エネルギーの一部を自給自足しています。
お米は常食のうるち米の他に、正月のお餅用にもち米、
藁細工用には緑米(みどりまい)を。
麦は小麦粉用の小麦に、麦茶用の六条大麦、試験的にハダカムギを。
大豆は加工用も含めて数種類。これら主要な農作物は、土地に合うよう種取りから行っています。
野菜類は基本的に土地に合っていたり、交雑しにくいものを選んで栽培していますが、
栽培するものを選ぶ上で最も重要な基準となっているのは、ご夫妻自身が本当に食べたいかどうか。
蓮根がどうしても食べたいからと蓮田を作るところから始めたり、
ニガウリは好きではないから作らなかったり。
メロンは甘過ぎて苦手だから代わりにマクワウリで、というように。
ご主人は県南部に数多く遺る第二次世界大戦の戦争遺跡についても詳しく、
農業は平和の象徴だからと「帰農」されたとか。
元保育士の奥さんはお料理上手で、何よりも私と同じく食べることが好き。
調味料はもちろん、豆腐やこんにゃく、カレールゥまで自家製です。
お客さまに分けるほどは作っていないけれど、という自家消費用の裏作物もたくさんあって。
米粉や小麦粉、乾麺、黒落花生やトマトソース、竹の子の水煮…
そういったものをお土産に頂くと、つい、ニンマリしてしまいます。
お腹だけでなくココロまで満たしてくれた、Y農園での援農体験
Y農園のお二人からは農作業の他にも学びがたくさんありました。例えば、雨の日に、オクラの種を選りながら聞く「種子法」の話であったり。
例えば、第二次大戦中の戦跡が遺る山の中腹の畑で、草取りをしながら聞く、
特攻機の話であったり。
どこまでが自分たちの暮らしや仕事に関わってくるのか、という政治や社会の話は、
生命の元となる食べ物を作る農作業を生業とする彼らが語るからこそ、
我が身にリアルに迫ります。
Y農園での援農を始めてから、我が家の食卓だけでなく、
私の心までも豊かになったのは言うまでもありません。
今月の「援農」日誌
〜稲が育ち、田にはもう入れない七月。
あとは豊作を祈るだけ

▲トンボの羽化を目の当たりにできるのは、田んぼ作業の特権
Y農園の田んぼでは、一本植えの稲が順調に分けつ(株分け)しつつ、丈を増しています。
ここではお米も種まきから。一本植え用の育苗ポットに2、3粒の種モミをまき、
それをハウスではなく、水苗代という育苗専用の田んぼで、ゆっくり育てると苗の出来上がり。
一本植えは育苗にも、田植えにも、除草にも、手間と時間がかかるけれど。
こうして大切に植えられた稲は、田んぼの養分を着実に吸い上げ、一本が二本に、
そして四本に…と順調に葉茎の数を増やしていきます。
一本あたりの収穫量が多いのも特徴です。
さて、稲の種まきから3ヶ月、今年はザリガニの被害よりも雑草の繁殖がひどく、
先月は「補植(※)」と除草作業をお手伝いしました。
※補植:田植え機が植え残したり、ザリガニに苗が切られた箇所に
手差しで稲を植えていくこと。
ザリガニがハサミで稲の茎を切ってしまうのは、故意ではないのだけれど。
田植え直後のか細い苗は、あのハサミにつかまれただけで簡単に切れてしまいます。
除草は、手押しの機械を往復させた上に、機械の届かない稲の周りに、
しつこく残るウシケやホタルイ、コナギといった水生の植物を、手で取っていきます。
とは言っても、稲の周りの泥を両手でかき混ぜると、ふわっ雑草が浮いてきて除草作業は完了。
また田んぼには、膝上まである、愛用の「田んぼ長靴」を履いて入水します。
補植にしても除草にしても、人が田んぼに入って歩き回ることで、泥の中のガスが抜けて、
健康な状態になるそうです。
半日入っただけで、腰も背筋もかなりつらいけれど。
足腰も鍛えられて、田にとっても人にとっても、一石二鳥と思いたいところ。
お天気の日には、ウスバキトンボやシオカラトンボの羽化に遭遇することも多く、
神聖な気持ちに。
と、田んぼに入る作業は六月まで。
稲が育った七月は、もう入水することも叶わず、あとはただ豊作や、
台風前に脱穀が無事終わることを祈るのみ。
七夕しかり、七月は祈りの月なのかもしれません。
多雨で畑に入れない日も
~夏野菜のお世話に、ボカシ作り

▲控えめでかわいらしい、瓜科の黄色い花
気温が高くなると夏野菜の成長が著しくなり、カボチャに敷き藁をしたり、
トマトに支柱を立てたりしています。
四月、ポットにまいたトマトやピーマンのその種はわずか2mmの薄くて軽いものだったのに。
畑に地植えした途端、膝丈ほどまで育って感慨深い。
ここ県南部の山間地は、ひどい粘土質で水捌けが悪いため、
雨が続くと畑に入ることができなくなります。
ホントはゴマ畑の草取りをしたいんだけれど…
そう思いつつ、裏庭で肥料にする「ボカシ」作り。
生ゴミ堆肥に米ヌカを混ぜて発酵させたボカシは、匂いもなく、
サラサラで使いやすく、効き目も良いよう。
このボカシは梅雨が明けたら大豆畑に使う予定。
我が家の生ゴミ堆肥も、お役に立てて嬉しい限りです。
これからも緩く長く。
農に手を添えて、思いを寄せて

▲空き畑は草を使った緑肥で土壌を改良するのに使ったり、防風に役立てたりする
バテやすい私が、こんなにも長く援農に携わることができたのは、
農業や自然が、私の知的好奇心を刺激してやまないから。
農業に関わる人たちの、社会問題と深く関わりつつ、美味しいものを食べたい、
育てたい、そして届けたい、という真摯な姿が魅力的だから。
そして、美味しくて安全なお米や季節の野菜、加工品が、
お金に頼ることなく、自分の労働力と引き換えに手に入るから。
農業って愉しいだけじゃない。でも、大変なだけでもない。
さて、愛用のゴム引き軍手を手に、今日も元気に行って参ります!
オーガニック食品やコスメをお得に買えるオーガニックストアIN YOU Market
IN YOU MarketIN Y0U Marketのおすすめオーガニック農産物
こちらの記事もおすすめです!
「だから農薬を使っているんです。」農薬の最大の被害者は農家自身|日本の農業の実態と、有機農業を育てる5つの方法【注目発表】有機農産物を食べれば農薬の体内濃度が50%以上も下がる!?|再認識したい、ネオニコ系農薬の多大なる危険性
「虫が食べるほど安全な野菜」は大間違い!?オーガニックの未来を切り拓く「炭素循環農法」とは

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)