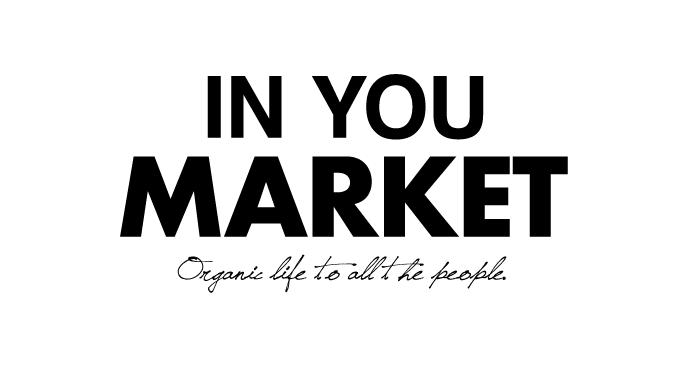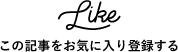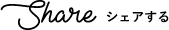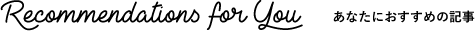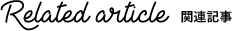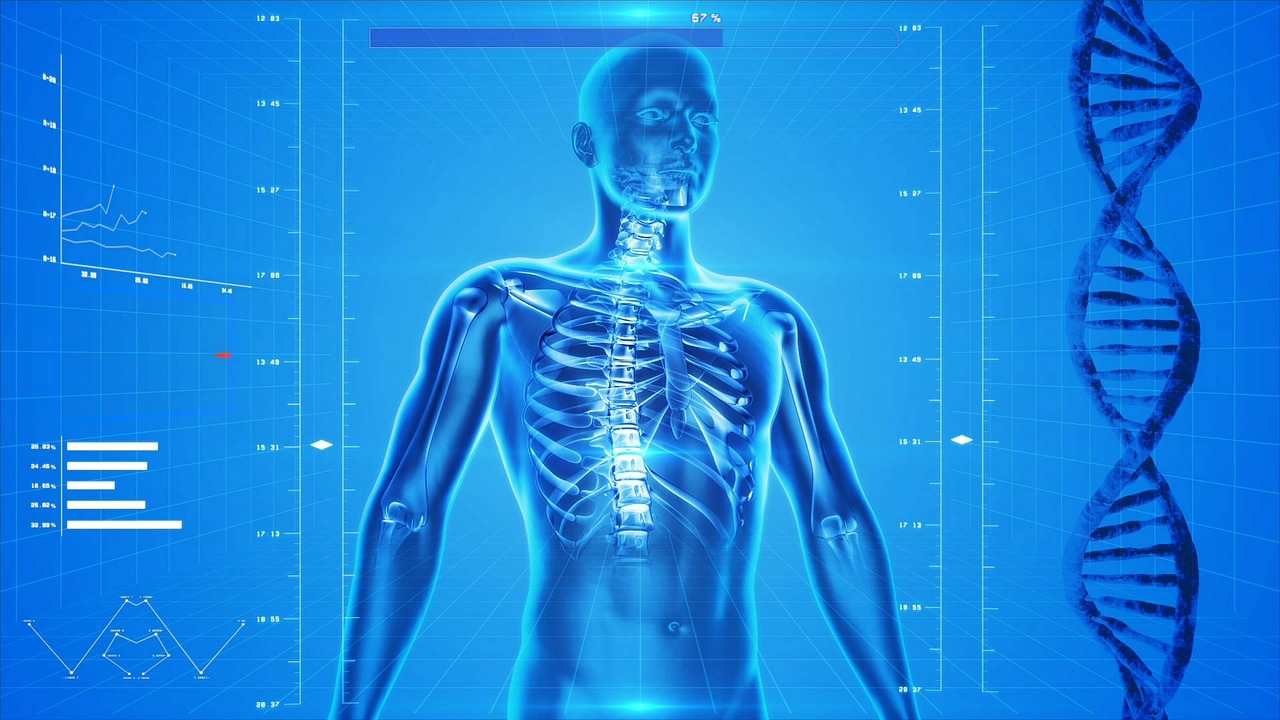鼻水の質や種類によって対策は変わります|看護師が教える「お家でできる鼻水・鼻づまりのホームケア方法5選」

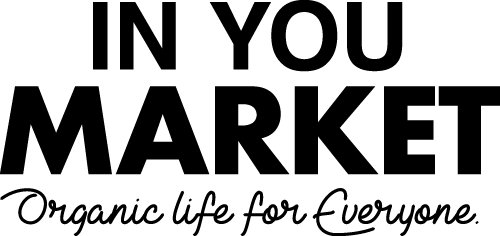
本物のオーガニックが見つかるオーガニックショップ
こんにちは、看護師のほんのりです。
こどものアトピーをきっかけに、
こども自身の自然治癒力を育もうと、できるだけ自然派のくらしを実践しています。
からだの不調の中で、鼻のトラブルは最も一般的で多い症状の一つです。
風邪やアレルギー性のものが殆どを占めますが、不快感の強い症状です。
症状が重いとなかなかやっかいで、頭がボーっとして集中できなかったり、
においが分からなくなってしまうと、食事の味もわからなかったり。
鼻声になってしゃべりにくかったり、
鼻呼吸がしづらくなるため、口呼吸になりやすく、その結果のどがカラカラに乾いたり、
空気中のほこりやウイルスを吸い込んでしまい、結局咳に繋がったり。
からだというのは、全体でバランスをとっていて、
すべての臓器がお互いを支え合いながら、時に代償として機能し合いながら成り立っています。
なので、一つの機能が崩れると、他も連鎖してバランスを崩しやすいのです。
鼻はすぐれたはたらきもの

鼻水は、鼻腔粘膜の乾燥を防ぎ、鼻を通って肺に入る空気に湿気を与える役割があります。
肺が、酸素を取り込むのにベストな温度・湿度となるように自動で調節しているのです。
そのため、風邪でない時も、自覚はないけれど鼻水は常に作られているのです。
また、もう一つ重要な役割としては、
鼻の中に入ってきたほこり・花粉・ウイルスなどの異物を排除するのも、鼻水の重要や役目。
要するに、空気清浄機能なのです!
からだの入り口の一つですから、門番のような役割ですね。とても重要な部位なのです。
東洋医学的視点からみた鼻水・鼻づまり

東洋医学的視点から見た鼻の症状は、肺の機能低下と考えられています。
原因を見分けるのは、鼻水の状態です。
黄色っぽい鼻水は、肺に熱がこもっているのが原因。
頭痛・のどの渇き・発熱など炎症症状を伴います。副鼻腔炎なども、このタイプに当てはまります。
薄い鼻水が大量に出るのは、寒邪と湿邪が肺の機能を阻害し、余分な水分が鼻にあふれています。
冷えで悪化するのが特徴で、鼻をかめばラクになります。
また、ちょっとしたことで水っぽい鼻水が出るのは、脾(消化器)の機能が弱まっていることが原因の場合も。
消化器が弱っているとからだのエネルギーが作れずに温められず、冷えて鼻水がでる場合もあります。
出せないことの方が要注意!?
咳や鼻水、痰、湿疹、発熱、下痢、嘔吐など、出すことはからだから有害物質を排除しようという自然の生体反応です。
ですから、基本的にこういった症状は、薬で止めさせるより、出してしまう方がからだにとって大事です。
それよりも、むしろ出すべきものが出せないでいること、
いわゆる詰まる状態の方がはるかにやっかいで、それに対しての注意やケアは必要です。
中耳炎や副鼻腔炎などは、鼻水が外に出せないことから引き起こる病気の代表例です。
重症になると鼓膜にまで炎症がおよび、手術が必要になってくるケースも多くあります。
ですから、より注意してケアをする必要があり、場合によっては西洋医学に頼るケースも必要でしょう。
何か症状という形で出すことは、からだにとって大切な浄化作用なのです。
参考:お母さんは世界一の名医 西原克成 著、Newton 別冊 体と体質の科学
鼻水の質別 おうちで簡単ホームケア
鼻水の質によって原因は違うとお伝えしました。
ではその原因別に、おうちで出来る簡単ホームケアをいくつかご紹介します!
黄色っぽくて粘っこい鼻水の場合
肺に熱がこもっていることが原因です。
前述しましたがその他の炎症症状を伴う事が多く、頭痛や発熱など総合的な対応も必要になるケースもあります。
肺の熱を冷ますことで改善を試みましょう。
ツボ
顔にある、印堂と迎香というツボは、鼻水・鼻づまりの特攻ツボです。
呼吸を整えながら痛くない、気持ちの良い程度に5回ほど押しましょう。
副鼻腔炎を伴っているなど炎症症状が強い時は、通常より痛く感じるかもしれません。
あまり無理して押したりせずに、自分で強さを調節しながら軽く刺激を与えてください。
食べ物

肺の熱を冷ます作用のある食材が適しています。
豆腐・ごぼう、バナナ、梨、レモン、セロリなど。
ペパーミントなど清涼感あるものもおススメです。ミントティーなども効果的でしょう。
粘性が強いときは水分補給をこまめに行い、少しでも粘性を和らげると鼻水の排出も促進されます。
水っぽい鼻水が大量の場合
肺に寒湿の邪が進入したことが原因です。冷えで悪化しやすいため、冷えを避けることが第一選択。
からだを温め、また体内にある余分な水分の排出を心がけましょう。
また、脾(消化器)の働きが低下した場合も、鼻水が出やすくなります。
脾は、肺に気を与える役目がありますが、脾の働きが衰えると結果として肺の機能低下も引き起こします。
①肺の機能を高めるツボ
寒湿の邪を追い出す効果のある、肺愈を刺激します。

頚を曲げた時でっぱる骨から3つ下の骨をみつけ、左右のそれぞれ指幅2本分外側。
指圧の刺激でも効果的ですが、
カイロやお灸などで温める刺激を与えると、より寒湿の邪を追い出す効果が期待できます。
②脾の機能を高めるツボ
●足三里(あしさんり)
.jpg)
すねの外側の筋肉が始まるところ。膝のお皿の下端から指幅4本分下、押したときに筋肉がややへこむ所。
●陰陵泉(いんりょうせん)

足の内側をひざ下から膝にむかってさすっていくと、膝の内側辺りで大きな骨にぶつかる部分。
からだを温める

寒湿の邪が侵入したのが原因のため、冷えを避けることが第一です。
からだを温め、体内の余分な水分を排出することが必要です。
原因が脾であっても、肺であっても、共通して言えることはからだを温めること。
服装を調節することや温かい食事・飲み物を摂る、
上記のツボ以外にもカイロやお灸でからだを温めるのも効果的です。
鼻は随時かみ、鼻水を外に出すこと、
からだが温まると循環が良くなり、尿の生成も促進されるので、
尿として体内に溜まった水分も排出していきましょう。
また、からだが冷えていると、からだを巡る気・血・水の巡りも滞りがちになり、
結果としてからだの免疫力も低下します。
ピンポイントに咳に対するアプローチをしても、ベースとしての免疫力が弱まっていたら本末転倒ですよね。
とにかく冷えはからだにとってマイナスの要素しかありません。
しっかりとからだを冷やさないように努めましょう。

女性特有のや悩みを抱える現代女性の救世主!こだわり天然ヒノキ椅子と野生・農薬不使用のよもぎの「自宅でカンタン日本製よもぎセラピーセット」
¥ 8,640 ~ ¥ 129,600 (税込)
自分のからだと対話しよう

インドに伝わる伝統医学、アーユルヴェーダでは、鼻は脳の扉・入り口と言われています。
一時的には仕方ないにしても、やはり入口は風通し良く、滞らせずにおきたいですよね。
いくら病院行って薬を飲んでいるからって、薄着でからだの冷えるようなものを食べていたり、
そんな過ごし方をしていては、本末転倒。
症状は、からだからのサインなので、
何が原因で、今からだでどんなことが起こっていて、
それに対して何が必要なのか、どんな対策をすればいいのか、
こういったことは知識として知っておいて損は無いはず。
ホームケアのメリットは、より自然でからだに負担がかからないし、
材料さえあれば外出せずとも手軽にできることです。
そして、いろいろ試してみながら、自分のからだとも対話する時間を持つことも大切です。
からだを温めるとラクになったな
このツボは効き目があった
冷えると鼻水悪化するんだな
そんなことを感じながら、からだと向き合い、
労わる時間を是非持ってみてください。
IN YOU Marketのオススメオーガニック商品
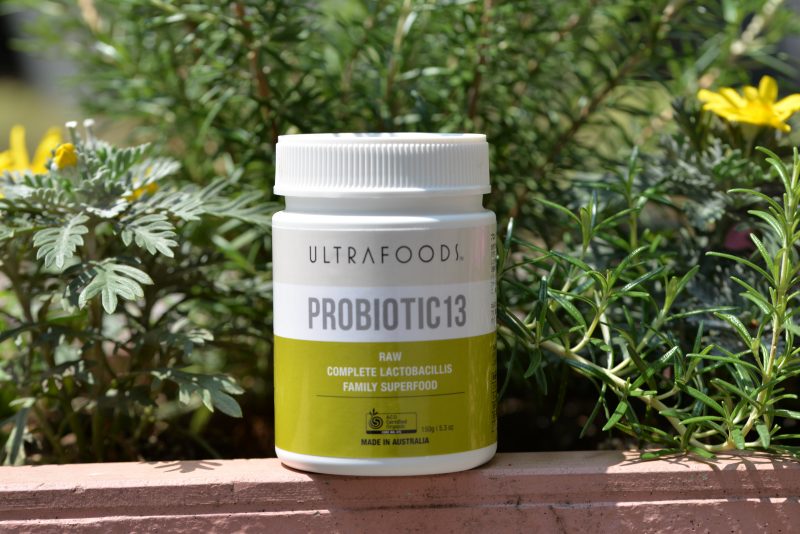
オーガニック乳酸菌パウダー。腸内環境対策に。13種類の乳酸菌/酵母菌と25種類のホールフードを自然発酵。 1〜3個セット(割引あり!)
¥5,900 ~ ¥ 15,044 (税込)
この記事を読んだ方にオススメの記事
忙しい毎日でも2ステップでお出汁を取る簡単な方法『水出汁』のやり方|疲労回復成分たっぷり・肥満防止にも、出汁を取り入れよう夏は夜にも熱中症のリスクが!意外と知らない正しいエアコンの使い方と寝具の選び方|暑くて寝苦しい季節での快適な睡眠方法6選
市販虫除けスプレーにはアレルギーや肌荒れを起こす成分が含まれている?!今すぐ知っておきたいお家で簡単にできる虫除けアロマスプレーの作り方【オーガニックなうまくんシリーズ】
IN YOUライター募集中!
あなたの時間を社会のために有効活用しませんか?
年間読者数3000万人日本最大のオーガニックメディアの読者に発信しよう!
IN YOU Writer 応募はこちらから

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)