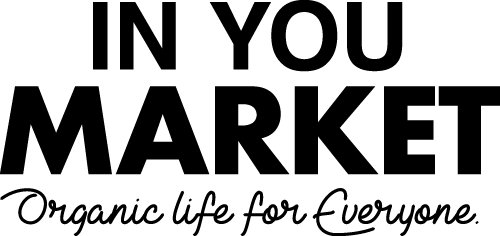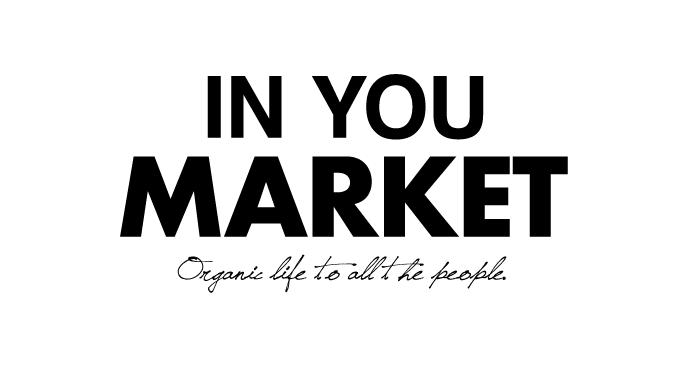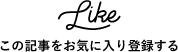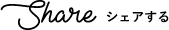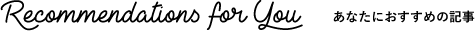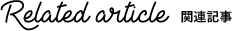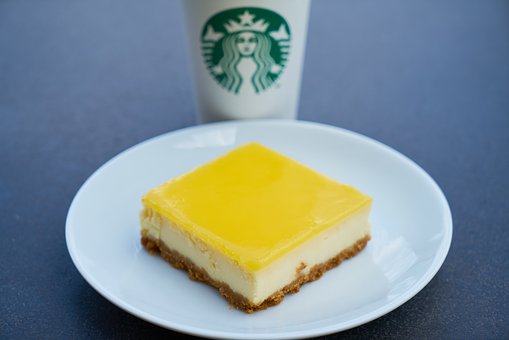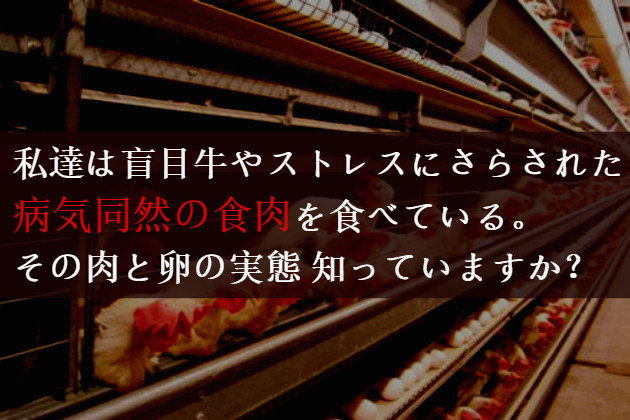葛とゼラチン「東洋医学から見た性質の違い・使い分け方」を薬剤師がお伝えします。 葛の秘められたイソフラボンの力とは。

こんにちは!薬剤師のNOZOMIです。
本日は、「葛」についてお話ししていきたいと思います。
葛、と聞くと、くず切り、くず餅、くず湯、あんかけ、葛饅頭・・・と
美味しいモノばかりですが、葛もれっきとしたお薬の原料だという事を知っていましたか?
そう、皆さんおなじみの「葛根湯」です。
葛根は、葛の根のことを言います。
普段目にする葛は、葛粉として既に加工されてしまっているので
ピンとこない人もいると思いますが、葛根を粉にしたのが葛粉なのです。
このトロッとした葛には隠された力が秘められています。
どんな力があるのでしょうか??
葛とゼラチンの違いは食感だけ?東洋医学で捉える性質の違い
葛とゼラチンの違いとは?

葛は、マメ科のクズ属の植物です。この根を乾燥させて粉にしたものが葛粉です。
主成分は、炭水化物です。
ゼラチンは、動物の骨、皮、腱の主成分であるコラーゲンを加熱して、取り出したものです。
主成分は、動物性のたんぱく質です。
似ているようで、動物性と植物性、炭水化物とたんぱく質と、性質は全然違うのです。
生薬としての葛根

「葛根湯」が代表されるように、葛根は様々な漢方薬に配合されています。
そんな、生薬としての「葛根」は、辛温解表剤に分類されます。
解表剤は、大きく2つに分けることができ、辛涼解表剤という分類もあります。
葛根が分類される辛温解表剤は、読んで字のごとく、
辛味によって、身体を温め、身体の表面にいる毒素を発散・解毒させるお薬です。
葛根の他にも、麻黄、桂枝、細辛などがあります。
主に「風邪(ふうじゃ)」に対して葛根は強みを発揮しますので、
風邪薬に使う漢方薬に多いのも納得ですね。
葛根が配合されている漢方薬は以下の通りです。
葛根湯、葛根湯加川芎辛夷,独活葛根湯、桂枝加葛根湯,升麻葛根湯,参蘇飲,などです。
生薬としてのゼラチン
ゼラチン、実は生薬でもあるんです。「新農本草経」によると、生薬とは、植物由来だけでなく、
動物由来・鉱物由来などを含めて約365種類あるといわれています。
面白い生薬としては、セミの抜け殻をそのまま乾燥させて使う、蝉退という生薬もあります。
ゼラチンは、阿膠(あきょう)といいます。
厳密にいうと、阿膠はロバの皮を煮詰めて作る褐色~赤褐色の濁りのある生薬ですので、
一般的に流通しているゼラチンとは違います。
一般に流通しているのは、豚や牛、また魚由来のものが多く、
また精製されているものが大半です。
阿膠は、生薬としては、「補血剤」に分類されます。
血を増やす補血剤の他に、阿膠は止血としての作用も持ち合わせているため、
痔や不正出血などの漢方薬に配合されることが多いのが特徴です。
代表的な漢方薬は、温経湯や芎帰膠艾湯ですね。
医薬品としてのゼラチン
阿膠としてのゼラチンではなく、通常のブタや牛、魚が由来のゼラチンの中には、医薬品として認可されているゼラチンもあります。
主に止血剤として使用されることが多いのです。
また、阿膠が取れにくくなっている昨今、
阿膠の代替品としてゼラチンが配合されている漢方薬もあるので、
成分表を見てみるのも面白いかもしれませんね。
ゼラチンと葛の使い分けとは・・・?

上記で説明したように、ゼラチンと葛は似ているけれども持っている性質は違うものです。
そのため、使い分けしていくのがいいですね。
ゼラチンは、動物性という事もあり、血を補うとはいえ、大量にとると血が汚れやすくなります。
また、原料によってはアレルギーが出てしまう事もありますから、安全に使うのがいいですね。
血を止めたい、ちょっと血を補いたい場合にはゼラチンがいいという事になります。
日常使いよりは、その時々で取り入れましょう。
一方、葛粉は、植物性で安全なように見えますが、実は流通しているものの多くは、
片栗粉などのでんぷんを追加されたものが多く、葛のみでできている葛粉は高価です。
高価ではありますが、葛のみでできている葛粉は、
消化も良く、身体を温め、邪気を発散させる力もあるので、
風邪や胃腸が弱っているときにはピッタリです。
いきなり、抗生物質など風邪薬に頼る前に、くず湯に頼ってはいかがでしょうか?
葛の秘められた力、イソフラボンとは?
イソフラボンにも種類があった!?

皆さんは、イソフラボンと聞くと、「大豆イソフラボン」が真っ先に上がってくると思います。
実は葛にもイソフラボンが含まれているのはご存知でしたか?
イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンに似た形をしていて、
体内に吸収されると、女性ホルモンのような働きをしてくれるので、
更年期や婦人科のトラブルがある方は好んで摂取している方も多いと思います。
一方で、イソフラボンの過剰摂取によるトラブルがあることも事実です。
そのため、上限摂取量が定められたという経緯もあります。
出典:食品安全委員会
そこで、出てくるのが、アグリコン型とグリコシド型です。
元々、大豆イソフラボンはグリコシド型といって、糖がついていて、吸収されにくい状態です。
腸内細菌によって、この糖が分解され、外れると吸収が良くなります。
吸収が良くなった大豆イソフラボンのことをアグリコン型イソフラボンと言います。
そのため、腸内環境が良くない人は、アグリコン型イソフラボンに変換する効率が悪いため、
いくらとっても変化が出ない・・・なんてこともありますね。
葛のイソフラボンは何型?
イソフラボンは、大豆だけに含まれるわけではありません。アグリコン型が多く含まれると有名なところでは、レッドクローバーですね。
ヨーロッパを中心に、サプリメントとして摂取されることが多いようです。
では、葛のイソフラボンはアグリコン?グルコシド?どっちなのでしょうか?
出典:『葛澱粉および葛葉におけるイソフラボン含有量調査』
葛は、大豆より吸収のいい形であるアグリコン型のイソフラボンが多いと聞くと、
過剰摂取になるのでは、と躊躇してしまう方もいると思いますが、
問題なさそうで良かったですよね。
ただし、ホルモン剤を服用されている方は、
医師または薬剤師にきちんと確認していただくのがいいですね。
食品でとる量とホルモン剤に含まれている量は全然違いますので、
安易に使うのは注意しましょう。
新たな可能性、イソフラボンによる生活習慣病の予防とは?

実際にイソフラボンに期待できることに、どのようなことがあるのでしょうか?
まず、1つ目は更年期です。
更年期は、女性が閉経に向かう事で、
分泌が減少するエストロゲンやプロゲステロンのバランスが崩れて起こる様々な症状です。
不眠、ホットフラッシュ、イライラや情緒不安定、月経不順などなど様々です。
2つ目は、骨粗しょう症です。
こちらも女性の閉経後に多い症状ですね。エストロゲンが減少することにより、
骨を作る細胞と壊す細胞のバランスが崩れ、骨がもろくなってしまいます。
他にも、高脂血症の予防や、肌のはりや髪の艶、女性らしい身体つきなどなど
女性は、減らしたくない成分の1つではないでしょうか?
また、新たな可能性として、女性には必見のダイエットな話題です。
大豆イソフラボンでの検討にはなるのですが、
葛に多く含まれるアグリコン型のイソフラボンの1つであるdaidzeinは、
以下の記載のある文献が発表されています。
ダイゼインは骨格筋においてERRαを介して
PDK4, MCADなどの発現を増強し,脂質燃焼を増強する可能性が示唆された
また、葛の花のエキスで脂質に影響を与えたという文献もあります。
出典・引用:葛花抽出物が血清脂質および体脂肪に与える影響
大豆イソフラボンによる転写因子ERRαを介した 骨格筋エネルギー代謝関連遺伝子制御の検討
葛にイソフラボンが含まれていること、意外だったと思いますが、
このようにいろいろな力を秘めている葛を生活の中にうまく取り入れてみませんか?
IN YOU Market限定のオーガニック葛はいかが?
この記事を読んだ方にオススメの記事
4月23日 IN YOU 3周年記念!春のデトックスオーガニックパーティー開催!新しい出逢いで2019年を満喫しよう!精神安定はこれで対策!体質別で考える鬱病。 メディカルハーブコーディネータがー選ぶ鬱にオススメのハーブとは?
世界唯一のギリシャ・ヒオス島で生産される樹脂「マスティハ」。木の樹脂が生み出す、次に注目されるスーパーフードとは?【オーガニックベンダーズ達の声 by IN YOU Market】
IN YOUライター募集中!
あなたの時間を社会のために有効活用しませんか?
年間読者数3000万人日本最大のオーガニックメディアの読者に発信しよう!
IN YOU Writer 応募はこちらから

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)