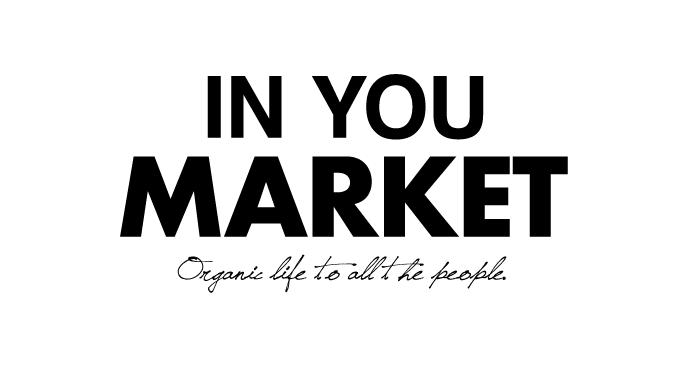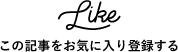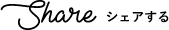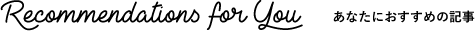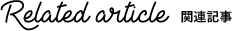果物の農薬や環境ホルモンを除去する方法|初心者向け農薬落としのコツ

果物の農薬や環境ホルモンを除去する方法|初心者向け農薬落としのコツ

これまで、同じシリーズで執筆をさせていただきました。
今日からでも簡単にできる!がんのリスクも懸念される、有害な環境ホルモンを軽減する方法はこれだ!!【魚編】
今日からでも簡単にできる!がんのリスクも懸念される、有害な環境ホルモンを軽減する方法はこれだ!!【肉編】
今日からでも簡単にできる!がんのリスクも懸念される、有害な環境ホルモンを軽減する方法はこれだ!!【野菜編】
実は、私たちがほぼ毎日口にする「フルーツ」「加工食品」の中にも注意すべき点が多くあります。
フルーツ

フルーツに関しましては、基本的には水洗いをよくして、皮をむくことが基本です。
理由は、農薬の使用量が農作物の中でもトップレベルだから。
多いものだと数十回以上の農薬を撒く場合もあります。
また、選ぶときは出盛り期のものを選ぶことが大切です。
そして野菜と同じように、生育が良いことも必要条件。
輸入果物のポストハーベストなどの問題もありますので、オレンジなどの皮でマーマレードを作るときは、しっかり選ぶことも大切です。
農薬だらけのジャムなんて、恐ろしくて食べられませんよね。

以下を参考に、安心で安全なフルーツを選んでみてください。
甘夏
 流水中でスポンジを使って30秒くらい水洗いをし、皮をむけば安心です。玉が大きく重く、肌が荒いものを選びましょう。
流水中でスポンジを使って30秒くらい水洗いをし、皮をむけば安心です。玉が大きく重く、肌が荒いものを選びましょう。出盛り期は4月から6月です。
| 食材 | 除去方法 | 選び方 |
|---|---|---|
いちご |
流水中に5分くらいつけておき、その後5回くらい振り洗いします。 ただし、へたは洗ってから取ります。 |
形のよいものを選びましょう。 出盛り期は12月から3月です。 |
りんご |
流水中でスポンジを使って30秒くらい水洗いをします。 皮をむけばより安心です。 切り分けたりんごを塩水にさらせば、褐色になるのを防ぐだけでなく、不安物質を塩水が引き出してくれるので、さらに安心です。 |
左右のバランスがよく、お尻の出っ張りが高いものを選びます。 出盛り期は10月から12月が中心です。 「ふじ」「国光」など晩成のものは12月から2月が旬です。 |
レモン |
流水中でスポンジを使って30秒くらい水洗いをします。 無農薬物の以外は皮をむき、レモンティーのときは、汁だけを絞って入れましょう。 |
輸入ものはポストハーベストの心配があるので、極力国産ものを選びます。 出盛り期は9月から12月です。 輸入ものは一年中出回っていますが、「DP」「OPP」「TBZ」不使用の表示のあるものを選ぶようにすると安心です。 |
グレープフルーツ |
流水中で5回くらい手で水洗いをします。 その後半分に切ってスプーンですくって食べる方法が一番安心です。 |
輸入量がピークの4月から6月のものが最も安心です。 |
みかん |
結構農薬を使うし、表面に添加物を含むワックスが塗られている場合があります。 ワックスを落とすにはティッシュペーパーや脱脂綿などを使い、焼酎などのアルコールで表面を拭くと良いです。 あとは皮をむいて食べるので、特に心配はありません。 |
形が偏平で、表面の物物がはっきりしているものを選びます。 出盛り期は12月から2月です。 ちなみに私は、信頼できる契約農家さんからお取り寄せしています。 |
オレンジ |
流水中でスポンジを使って水洗いをし、皮をむけば安心です。 | 輸入量がピークの4月から6月のものが最も安心です。 |
メロン |
皮ぎりぎりまで食べないようにしましょう。 | 出盛り期以外は農薬使用量が増えるため、旬のときに食べたほうが良いでしょう。 出盛り期は5月から7月になります。 |
バナナ |
皮をむいたら、軸から1cmほどを切り落して食べます。 ポストハーベスト農薬も軸から1センチ以上先にはしみ込まないので、これで安心です。 |
農薬の質からしても、フィリピン産より台湾産のほうが安心です。 出盛り期は一年中になります。 |
| さくらんぼ (チェリー)  |
ボールに水を流しながら10分くらいつけた後、5回ほど振り洗いをします。 | 国内産のほうがポストハーベストの心配がなく安心です。 国内産の出盛り期は6月、輸入ものは5~7月になります。 写真は国産の山田錦になります。 |
ぶどう |
ボールに水を流しながら10分くらいつけた後、5回ほど振り洗いをします。 大粒のぶどうは手で皮をむいてから食べます。 農薬の心配のある小粒のものは、皮を口に入れてむかないように注意しましょう。 |
粒がそろっていて、落ちにくいものを選びます。 出盛り期は8月から10月です。 |
すいか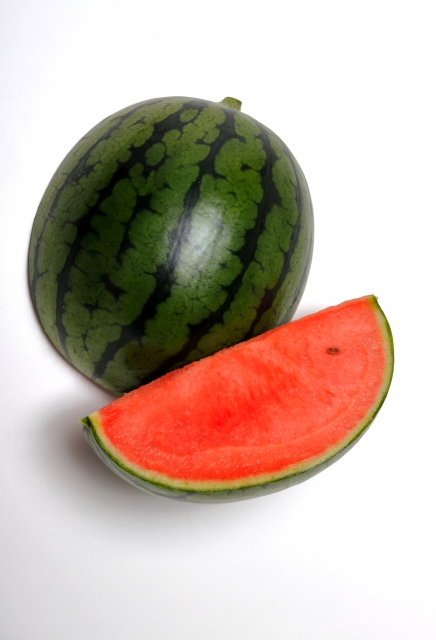 |
流水中でスポンジを使って5回くらい水洗いをしましょう。 食べるとき、皮を厚めに残せば心配はありません。 |
大きくて形のよいものを選びます。 出盛り期は5月から9月です。 |
もも |
流水中でスポンジを使って5回くらい水洗いをします。 食べるとき、皮を厚めに残せば心配はありません。 |
大きくて形のよいものを選びます。 出盛り期は5月から9月です。 |
なし |
殺虫剤をかなり使う果物のため、表皮下に残留している可能性があります。 そこで、流水中でスポンジを使って30秒くらい水洗いをした後、皮を厚めにむきます。 なしは果皮と果肉の間に酸があって、厚めにむいたほうがおいしいので、一石二鳥です。 |
左右のバランスがよく、形のきれいなものを選びます。 出盛り期は8月から10月です。 |
柿 |
流水で手でごしごし洗い、皮をむきます。 | オレンジ色が強くてむらがなく、ヘタが枯れていないものを選びます。 出盛り期は8月から10月です。 |
「”旬”のものを食べ、季節はずれのものを無理して食べない。」
ということです。
季節はずれのものには輸入物が多いですし、輸入物には”ポストハーベスト農薬”(収穫後の農薬、主に防腐剤・防カビ剤などを品物に直接散布する)の心配が、絶えず付きまといます。
スーパーに行けば様々なものが並び季節感なんてまったくありませんが、やはり出盛りのものはおいしいですし、農薬などの問題からも、”旬”のものを選びましょう。
加工食品
ここで最も注意するものは”食品添加物”です。また加工食品の容器から”環境ホルモン”が溶け出す可能性も指摘されています。
食品添加物は厚生労働省により健康への害がないことを認められた上で許可されているわけですが、多量に摂取すると発ガン性や、カルシウム不足による骨への悪影響、鉄分の吸収阻害による貧血を起こすなどの不安があります。
その中でも特に注意すべきもの、選び方、除去の仕方などを下記表にまとめてみました。
| 食材 | 除去方法/下拵え | 選び方 |
|---|---|---|
ハム・ベーコン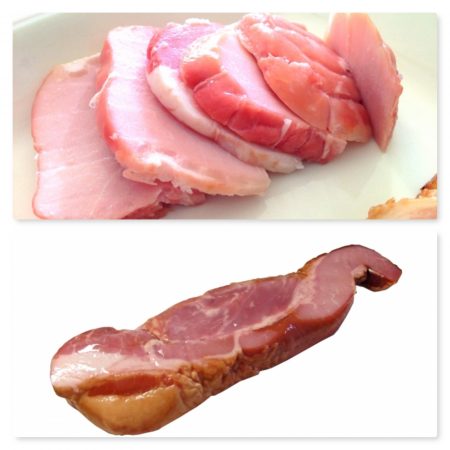 |
添加物が多い食材です。 ハムをサラダにするときなどは、10秒くらいお湯の中に入れて振ると添加物がかなり落ちます。 また、ハムやベーコンを炒めたりスープなどに入れるならば、1分くらい湯通ししてから使用するとさらに安心です。 |
よく使われている添加物で発ガン性その他で不安なものは、「ソルビン酸K」(保存料)、「リン酸塩」、「亜硝酸Na」「亜硝酸K」「硝酸K」(発色剤)、「コチニール色素」(別名カルミン色素)などです。 これらをすべて避けられれば良いのですが、なかなかそういった商品の種類は少ないものです。 そこでせめて「ソルビン酸K」のないものを選ぶことを心がけましょう。 この物質と発色剤の「亜硝酸」とで発ガン性物質ができるおそれがあるからです。 また「コチニール色素」も発ガン性、アレルギーが心配されており、ないものを選んだほうが無難です。 逆に「ビタミンC」の表示があるものを選びます。 「ビタミンC」は発色剤の害を減らしてくれます。 |
ソーセージ |
ハム。ベーコン同様に添加物の多い加工品です。 包丁で切れ目を入れ、ボイルすると安心です。 炒めて食べるときも1分くらいゆでると、添加物が半分くらいに減ります。 |
添加物については、「ハム・ベーコン」と、ほとんど同じです。 市販の商品の中にも、無塩せきで発色剤などを使っていないものも出ていますので、原材料名をよく確認してから買いましょう。 |
レトルトハンバーグ |
気になる場合は、包装から出したら沸騰した湯に30秒くらいつけていったん湯通ししてから調理します。 ハンバーグに絡めてあるソースは捨てて、手作りソースをかます。 これはソースに不安物質が染み出していることが多いからです。 |
現在はほとんど使用されていませんが、「ソルビン酸K」(保存料)、「リン酸塩」の表示のないものを選べば、あとはほとんど不安な添加物はありません。 ミートボールも同じです。 ただ、どんな肉が使われているかわかりにくい商品だということは、心に留めておいてください。 |
とうふ |
買ってきたらすぐパックから出して水につけます。 そうすることにより、添加物が溶け出しにがり臭さも取れておいしくなります。 すぐ食べない場合はタッパーなどに水を張って冷蔵庫へ入れておきましょう。 |
特に不安な添加物はないが、凝固剤として「塩化マグネシウム含有物」と表示してあるものが品質はよ良いです。 なお、消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル)は、不使用にこしたことはありませんが、さほどこだわる必要もないようです。 |
油揚げ |
熱湯をかけて油抜きし、それから調理に入ります。 原材料の油に少々不安のある酸化防止剤のBHA(酸化防止剤。発ガン性の不安が言われる)が使われていても、湯に溶け出してくれます。 BHAは原材料に表示されないため、油抜きは省略しないほうが安心です。 また、油に溶けやすい環境ホルモンが包装に含まれていても、このプロセスで除くことができます。 |
国産大豆を使ったものを選びたい場合は、「国産大豆100%」と、表示されたものを選びます。 それ以外は「国産大豆」とうたっていても、輸入大豆が入っていることがほとんどです。 |
ふりかけ |
ふりかけは食材と違って調理の過程で安心な状態にすることができないので、添加物がほとんどないふりかけ以外は、あまり回数多く食べないほうがよいでしょう。 特に子供向けのキャラクターふりかけには添加物が多い傾向があるので要注意です。 |
店頭で、原材料の表示をよくよく見比べて選ぶことが大切です。 よく見かけるもので特に避けたほうがよいのは、「コチニール(カルミン)色素」を使っているふりかけです。 その他によく見かける添加物はカラメル色素、クチナシ色素、紅花色素、カロチロイド色素、モナスカス色素、パプリカ色素、酸化防止剤(カテキン)、甘味料(甘草、ステビア)などですが、この中で特に甘味料の「ステビア」「甘草」もできれば避けたほうがよいでしょう。 |
漬物 |
包装から出したら、まず漬け汁は捨ててしまいます。 できれば一回サッと水洗いして食べれば、さらに添加物が減って安心です。 |
原材料表示に「黄色4号」など数字がついた着色料が入っているものは避けます。 また「コチニール(カルミン)色素」、保存料の「ソルビン酸K」も避けます。 甘味料の「甘草」「ステビア」もなるべく避ます。 なお、増粘安定剤のキトサンに特に問題はありません。。 |
| 練り物 (かまぼこ) (さつま揚げ)  |
かまぼこはそのまま食べる場合も、薄く切ってからしゃぶしゃぶのようにサッと湯通しすると、切り口から添加物が出ます。 さつま揚げも、調理前に湯通しをすると、油分も抜けて一石二鳥です。 |
保存料の「ソルビン酸K」、「リン酸塩」、「赤色106号」などの数字がついた着色料、「コチニール(カルミン)色素」、また「植物性たん白」の表示があるものは避けます。 植物性たん白の製造時にはリン酸塩が使われるため、表示がなくても入っている不安があるので注意します。 甘味料の「甘草」「ステビア」もなるべく避けます。 |
チーズ |
特に気にする必要はありません。 | ********************* |
たらこ |
たらこを焼くときは焦げないように焼きます。 焦げの発ガン性物質不安だけでなく、「調味料(アミノ酸など)」が添加されている場合、グルタミンが直火の高温で加熱されて、発ガン性物質ができる心配があります。 |
「赤色3号」など数字がついた着色料や、「コチニール(カルミン)色素」を使っていないものを選びます。 着色料の変わりに発色剤(亜硝塩酸など)を使うことが多いですが、同時にビタミンCの添加が義務づけられ、発色剤の害を防いでいるといわれます。 しかし、魚卵の食べ過ぎ自体が胃がんのリスクがありますので、ほどほどに食べるのが良いでしょう。 |
つくだに |
買ってきたら保管温度に注意しましょう。 | もともとは保存食ですが、最近の薄味傾向で不安のある保存料「ソルビン酸K」を使ったつくだ煮もあります。 要注意は「リン酸塩」を使ったもです。 甘味料の「甘草」「ステビア」もなるべく避けます。 |
缶詰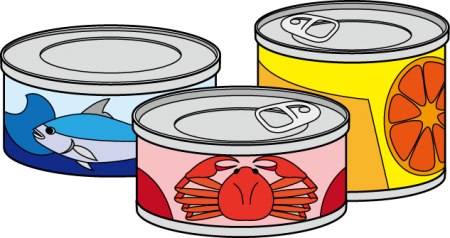 |
缶詰の内側は、ビスフェノールAを原料としたエポキシ樹脂でコーティングされていることが多く、長期間のうちに溶けて出してくる心配があるため、新しいうちに食べる方が安心です。 環境ホルモンは油に溶けやすいため、ツナ缶などの油の多いものは、汁を捨て湯通しして使うと安心です。 水煮の方がリスクは低いと思われます。 |
缶詰食は流行っていますが、できれば缶詰ばかり食べることは避けた方が良いでしょう。 |
冷凍食品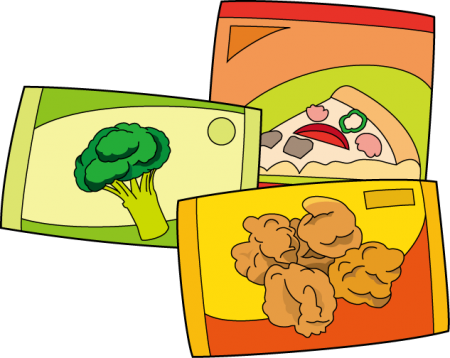 |
食材は旬のものを加工してありますし、小分けにも調理できるので大変便利ですが、そのまま電子レンジで温める物などで環境ホルモンが溶出する容器を使っているものは、容器を移し変えてから加熱すると安心です。 | 不安な添加物はさほどありませんが、避けるとしたら「亜硝酸Na」と「リン酸塩」です。 |
ベビーフード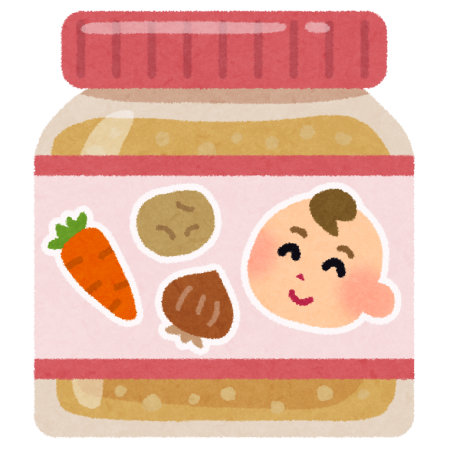 |
食べ残しは捨てる。 (ベビーフードは保存料を使用していないので細菌が繁殖しやすいため) |
「リン酸塩」の表示があるものは避けます。 表示に「リン酸Na」「ポリリン酸Na」「メタリン酸Na」「ピロリン酸第二鉄」などある場合も避けましょう。 これらは多食すると骨の形成阻害や、鉄分の吸収を阻害する不安があります。 |
持ち帰り弁当 |
いわゆるほか弁やコンビニ弁当の容器には、ポリカーポネート容器のものがよく見られるので、そのまま電子レンジで温めず、容器を移し変えます。 | コンビニ弁当などは添加物使用が多いので、よく注意して選び、毎日のように食べないほうがよいでしょう。 |
もちろん添加物がそれ自体いけないというわけではなく、全てが有害だというわけではありません。
私たちが今しなければならないことは、「選ぶこと」「その目と知識をやしなうこと」なのではないでしょうか。
メーカー自身にも「自分の子供にも安心して胸を張って食べさせられる」ものを作って欲しいと切望して止みません。

☆動画コンテンツIN YOU Tube『野菜の残留農薬大丈夫?スーパーの野菜の硝酸塩を測ってみた!』
オーガニック食品やコスメをお得に買えるオーガニックストアIN YOU Market
IN YOU MarketIN YOU Marketおすすめの安心・安全なオーガニックアイテム
この記事を読んだ方におすすめの記事
農薬にNON! 今、フランスで家庭菜園が大ブームなそのワケとは?農薬の使用量は世界一?日本の野菜や果物を安心して食べる工夫とは
日本の農薬と有機農業の現状|オーガニックが広まらない本当の理由とは?
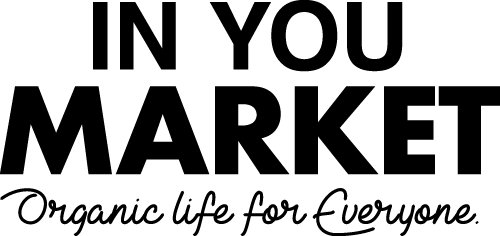
本物のオーガニックが見つかるオーガニックショップ

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)