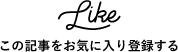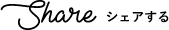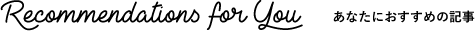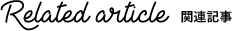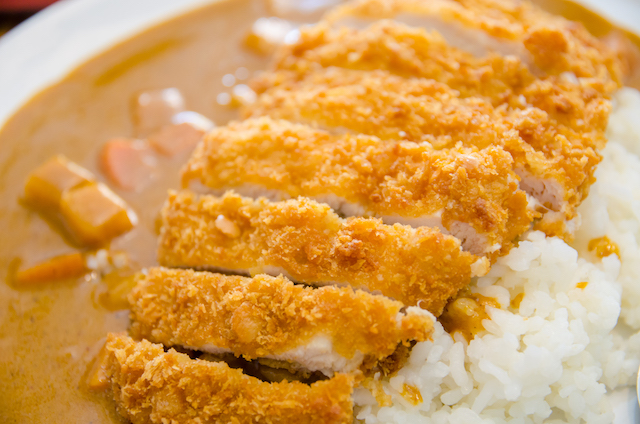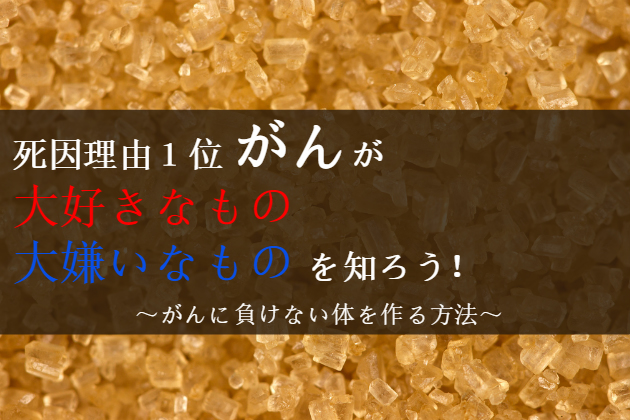「羽根突き」「凧上げ」は、正月を招き迎える魔術だった!?

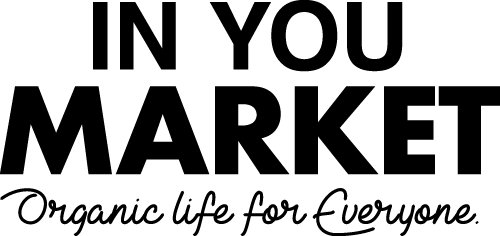
本物のオーガニックが見つかるオーガニックショップ
国によって年初は様々である
現在の太陽暦は古代ローマの皇帝ユリウス・シーザー(カエサル)が制定したもので、4年に1度のうるう年もこのとき制定されたと言われています。
中国の陰陽思想では、天・日・明・長・暑・福などを陽に、地・月・暗・短・寒・禍などを陰にあてて、
この陽と陰とによって世界を表しています。
冬至を境に太陽の光は日ごとに力が強くなるので、冬至の翌日が元日のはずだ、なんて話もあるほどです。
日本人は、除夜の鐘を聞きながら過ぎし一年の禊ぎを行います。
身体についている罪やけがれを洗い清めて新年を待つ、という意味があります。
新年を迎え、日の出の前の暗いうちから初詣をして、新しい一年の幸せを祈願します。
そして、初日の光を浴びたところで、「明けましておめでとうございます」と言いました。
これこそが日本人の古来からの慣習です。
日本ではじめて暦がつくられたのが推古天皇の604年、
百済を通じて伝わった中国の暦が採用されたのが始まりで、
江戸時代まで中国の暦が使われることになります。
太陰太陽暦では、立春が年初で、立春を含む月、あるいは立春の近くの新月の日が年初でした。
冬至より10日も過ぎて、節分・立春までにはまだ一月以上あるこの時期を、
どうして年の初めにしたのでしょうか。
太陰太陽暦とは、月が地球を一周する29.53日の12ヶ月分に相当する354日と、
地球が太陽を一周するのにかかる365日とに生じる差、「11日」をうまく工夫して、
月と太陽の両方の運行を考慮した、高度で科学的な暦が太陰太陽暦です。
四千年程前から中国の黄河流域で「農暦」として使われていたものが、
六世紀後半に日本に伝来し、修正されて、太陰太陽暦となったと言われています。
日本では1872年(明治5年)から、現在の1月1日を元日とするようになりました。
太陰太陽暦(月が地球を1周する時間と地球が太陽の周囲を1回転する時間を併せて作った中国の暦)から、
太陽暦(地球が太陽の周囲を1回転する時間を1年とする)に切り替えたので、
太陽暦の1月1日を元日としたのです。
以来、1ヶ月のズレが生じ、日本の伝統行事や、農・漁・林業等が混乱しました。
花の咲く時期から虫や鳥の出現は、新暦にはまったくあてはまりません。
立春や春分など二十四の節気で区切る、旧暦の太陰太陽暦の方がぴったり合うからです。
生態系のバランスがおかしくなったわけです。
国によって正月は異なるのはご存知のとおりです。
ヒンズー暦、イスラム暦、太陰太陽暦、太陽暦によるからです。
インドネシアのバリ島では太陽暦のほかに地方暦や宗教暦の正月がありますし、
タイでは太陽が次の黄道帯に入ることを意味するソンクーラン(タイにおける旧正月のこと)であり、
チャントラカティ(タイの旧暦)の新年は、政府によって4月13日から15日(仏暦・西暦)の3日間に制定されてます。
イランでは春分の日が正月です。
国や宗教によって年初は様々です。

世界に1人のあなたをパーフェクトにする世界に1つのオートクチュールオーガニック・フレグランス ”Fivele” (フィヴェール)【IN YOU Market 限定販売】
¥ 35,160 ~ ¥ 36,560 (税込)
> 商品の詳細はこちら正月を招き迎える魔術、「羽根突き」「凧上げ」

今はほとんど見かけなくなった「羽根突き」「凧上げ」ですが、
私が子供の頃はゲームもありましたが、こういった遊びもたしかにありました。
羽根つきは、室町時代に中国から「羽根を蹴る遊び」が日本に伝わったことが起源とされています。
羽根つきの羽根は、ムクロジという実に鳥の羽をつけたものです。
現代のように、医療が発達していなかった時代は、
多くの人たちが、感染症などの病気で亡くなった子供も多く、
子どもが病気にならないように、正月に子供に羽根突きで遊ばせたといいます。
なぜ羽根突きが病気を防げると考えられるのかというと、
当時は病気の原因は、牛や馬の血を吸う蚊だと考えられていました。
病気をもたらす蚊を食べてくれるのが「とんぼ」です。
羽根をトンボに例え、空気中に打ち、病気の原因である蚊を食べてもらうという意図があったと言われています。
もうひとつ、羽根突きは春を迎える行事であることが、五行説で説明されています。
羽根突きは鳥の羽で作られます。
鳥は金気に属します。金気の範疇に入るものは季節は秋です。
五行の相剋順で言えば、金気は木気(春)を剋します。
金気を弱めないと、木気(春)が出てこない、つまり春が来ないことを意味します。
金気を弱め、金気の象徴である鳥の羽で作られる羽根突きを空中に打ち、
春が早く来るようにと願ったというのです。
凧上げは「たこ」上げというが、これを辞書で調べてみると、別名「いか。いかのぼり」とあります。
ともに長い足が特徴です。
(実は、「いか」が古く、関西でそう呼ばれていたことに関東が対抗して呼んだのが「たこ」という名だそうです。)
「いかのぼり」とは何でしょうか。
これは紙で出来た「トンビ」を指します。
凧は中国起源ですが、もともと足のない形でした。
これを安定させ、トンビのように空高く上げるために足が付け加えられ、いかの姿となったのです。
で、なぜ正月に「いか」を空高く上げるのかというと、
「いかのぼり」の姿は、陰陽五行説の「火」気の象徴と言われています。
陰陽は交合し、天においては太陰(月)と太陽(日)また天体となり、
地においては木・火・土・金・水の五気となって万物を形作ったとされています。
世界は陰陽の二気から成り立っていることから、
五気は世界のすべてに流れる原理であると言い伝えられました。
干支(えと)と複合して、方位、年月日、時間などありとあらゆるものの支配原理でありますが、
とりわけ季節からは陰陽思想をとても強く感じます。
この記事を読んだ方にオススメのIN YOU Market商品
この記事を読んだ方にオススメの記事
冬の過ごし方一つで見た目年齢に大きな差が出ます。腎力をアップさせる「ノンシュガー黒豆あんこ」の作り方とおすすめレシピ2つ日本の伝統料理おせちまでも汚染している添加物。TPP11が年内に発効された日本で、日本の大型食料品店の取り組みはどうなるのか??
年末年始の食べ過ぎ・食べ疲れに劇的な効果を発揮する「七号食」のやり方について

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)