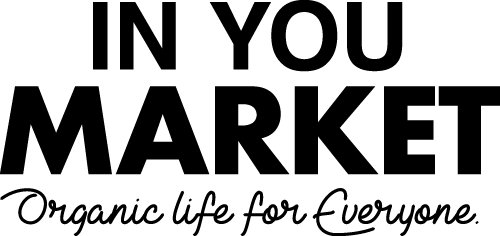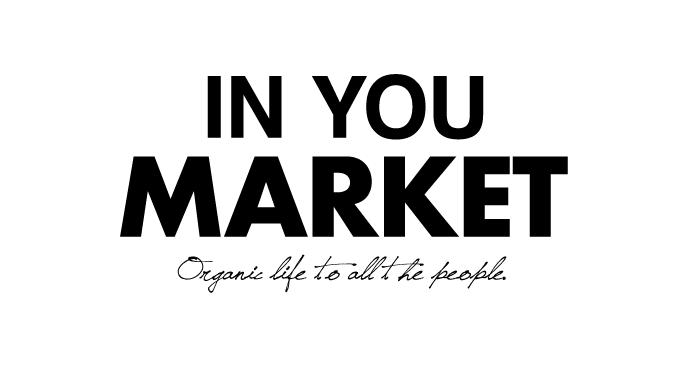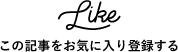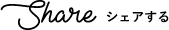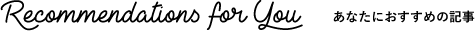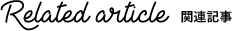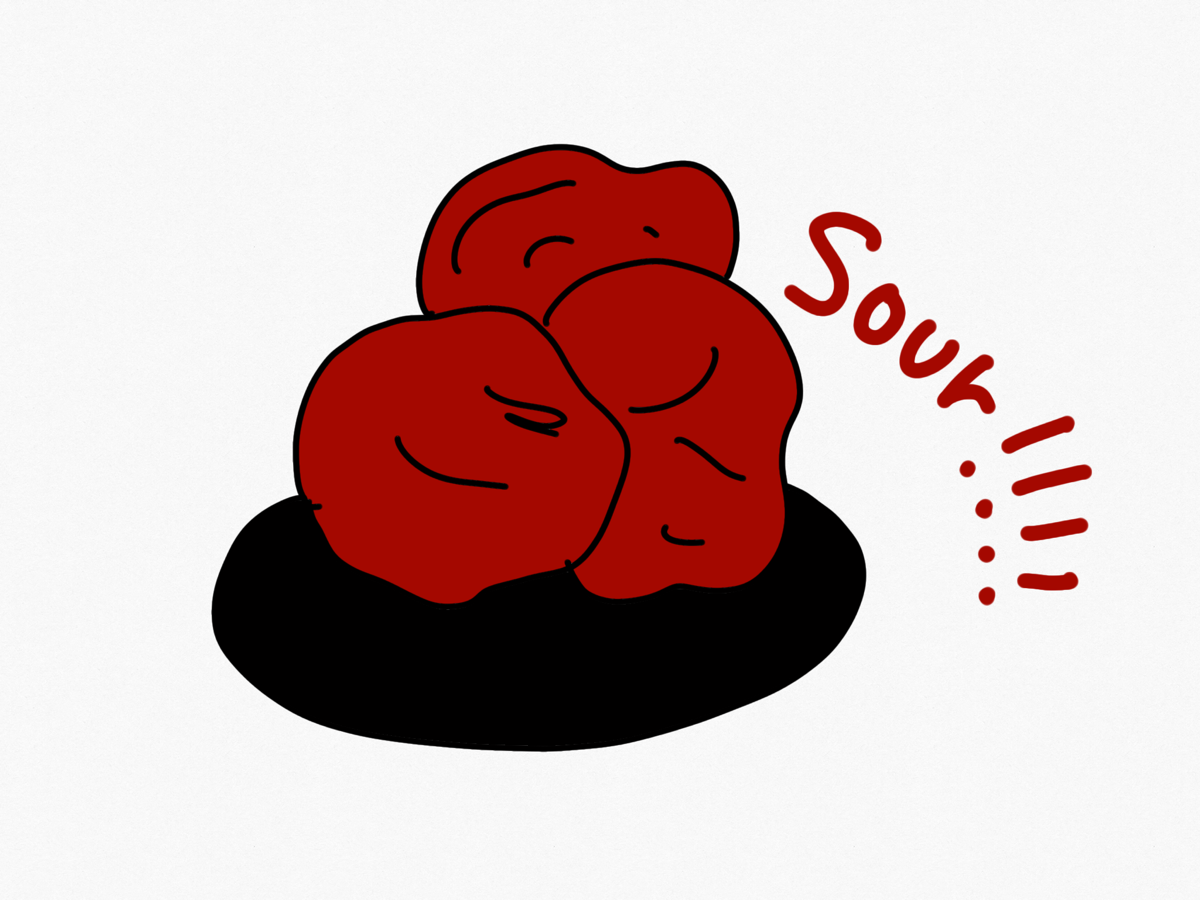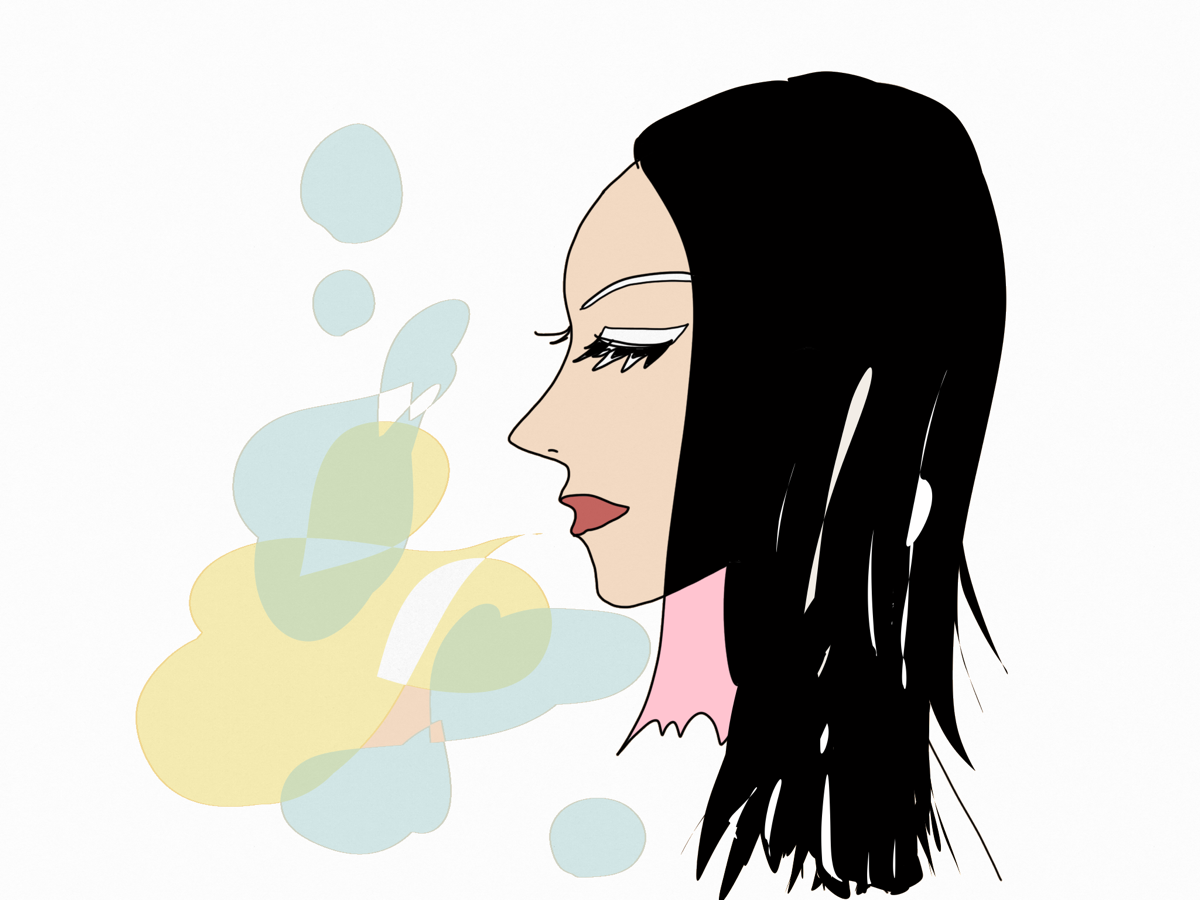汗をかいた体は乾燥状態や風邪に陥りやすい!体を内側から潤す東洋医学から見た秋の基本の養生法

暦の上での秋到来!
毎日暑い日が続きますね。私は沖縄在住ですが、お出かけするのをためらうほど毎日暑いです。
いつもは子供たちでにぎわう公園も、この時期は昼間は誰もいません。
滑り台なんて熱すぎて、お尻を火傷するレベルです。
こんなに暑いと、ついつい忘れてしまいがちですが、実はもうすでに暦の上では秋が到来しています。

【暦上の秋】
◆立秋 8月8日 秋が始まる日
◆処暑 8月23日 暑さが落ち着くころ
◆白露 9月8日 本格的な秋の始まり
◆秋分 9月23日 昼夜の長さがほぼ同じになる
◆寒露 10月8日 秋が深まる 植物に冷たい露がつく
◆霜降 10月23日 草が枯れ 霜が降り始める
気温は高くとも、陽気がピークの夏は終わり、冬が深まるにつれて陰気が増してくる季節となりました。
いや、まだ暑いし秋の話は早いでしょ!なんて言わないでくださいね。笑
整った空調に、季節にかかわらずどんな食材も手に入る。
そんな生活を送る私たち人間も
当然のことながら地球上にいる限り、自然界の一部であることに変わりありません。
季節の変化に柔軟に対応していくことは、
あらゆる不調を乗り越える「生きていく力」となります。
秋は夏の疲れを癒し
厳しい冬を迎えるための大切な準備期間
アリとキリギリスのお話は有名ですが秋は厳しい冬を乗り越えるための大切な準備期間。
それは、どんなに生活が便利になった今の私たちにも言えることです。
毎日暑いからと、クーラーをフル稼働させ
お昼は手軽に素麺で済ませて
入浴はささっとシャワーで
お風呂上がりのビールやアイス、、、
そんな生活を寒くなり始める直前まで続けていては、
夏の疲れを確実に引きずったまま冬を迎えることになってしまします。
もちろん暦上で秋だからと、急に秋の生活に切り替えることはありませんが、
秋が深まる前に夏の疲れを癒していきましょう。
まだまだ暑いからと、夏の延長のような生活を送って秋をうまく過ごせないと、
冬にも不調を起こしやすくなってしまいます。
ということで今回は、
秋の基本の養生法についてのお話です。
秋の養生法の基本

秋は、夏と冬の境目の時期。
一年で一番体力を消耗する夏の疲れを癒し、冬に備えて気を蓄える季節と考えましょう。
具体的には、質の良い睡眠をとることと、胃腸を休めること。腹八分目
温かい食事
よく噛んで食べる
など基本的なことをきちんと実行して、胃腸の調子を整えていきましょう。
この三つ、知識として知ってはいても意外とできていないものです。
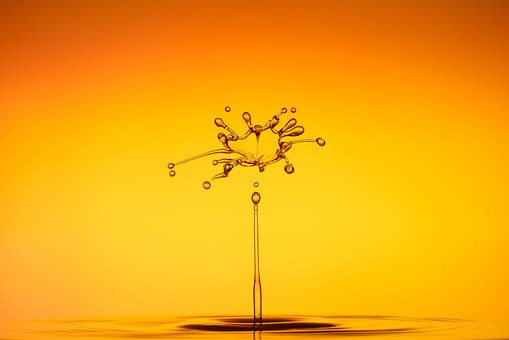
また、夏に汗をたっぷりかいた体は、知らず知らず乾燥状態に陥りやすいもの。
その状態で、これから秋が深まり空気が乾燥してくると、
たちまち乾燥に弱い臓器「肺」が不調をきたします。
「肺を補う」ということも秋を健やかに乗り切るためには重要なポイントとなりますね。
具体的な肺を補う食事法も、後ほどご紹介させて頂きます。東洋医学での「肺」の働き

東洋医学の考えのベースとなる五行論では、
秋は肺が不調をきたしやすい季節となっていて
秋の養生は、肺を補うことが基本となります。
◎肺は呼吸を司る臓器で、呼吸を行います。
呼吸は、清気(きれいな空気)を吸い、体内を巡って濁気(汚れた気)を排出するということ。
◎また、気温や湿度の変化から体調を崩すということは
誰しも経験があるとは思いますが、
そういった気候の変化による病因(=外邪)を免疫によって守るのも、肺の重要な役割と言えます。
◎肺の役割はそれだけではなく
気や水を全身に巡らせる働きも担っていて、
この働きによって皮膚が潤い、臓器に滞りなく栄養が行きわたります。
以上3点のような働きを担う「肺」が不調をきたすと
単に咳やのどの痛みだけでなく、全身の潤いのバランスを崩してしまうと考えられています。
喘息もちの方が辛い時期なのはもちろん
鼻水やのどの痛み、肌の乾燥、かゆみ、潤い不足からくる便秘、風邪をひきやすいなどの症状が出やすくなってしまいます。
身体を内側から潤す
「肺」を補う食事

秋は、乾燥に弱い臓器である「肺」を補う食材を積極的に取り入れましょう。
肺が潤うと肌も潤います。
乾燥肌の方にもおすすめの食材ですよ。
「潤い」といっても、ここでは単に水を飲みましょうということではありません。
薬膳では、大根、白ごま、白きくらげなど、白色の食材は肺を潤す食材と言われています。
また、身体を潤すとされる陰液(血・津液)は、酸味と甘味の組み合わせで補われると考えられています。
もちろん、甘酸っぱいからと言って、砂糖たっぷりのゼリーなどのことではありませんよ。
レモンとハチミツ、梅干しとごはんといった、自然の酸味と甘味の組み合わせのものを選んでくださいね。

【秋におすすめの食材一覧】
◎白い食材梨、大根、白ごま、白きくらげ、ハチミツ、ユリ根、れんこん、銀杏、山芋、カリフラワー
◎秋が旬の魚
鮭 さんま サバ
◎秋が旬の果物
柿 梨 ブドウ ざくろ 柿 栗
◎その他
タコ カキ ホタテ ほうれん草 サツマイモ
秋のおすすめレシピ1
ハチミツ大根

使うもの
・マヌカハニー 適量
・無農薬の大根の角切り
季節の変わり目に体調を崩しやすいという方は、
角切りにした大根をハチミツに一晩漬けて作る「ハチミツ大根」を
お湯で割ったものをこの時期から常飲するようにすると、風邪予防になっておすすめです。
レモンを少し絞ると、「甘味×酸味」 となってより身体を潤す作用が強くなります。
冷えがある方はおろし生姜を加えるとさらに良いですね。
秋のおすすめレシピ2
梨ジュース

肺を潤すとされる白い食材の中でも代表的なものが梨です。
特にのどの痛みや、炎症、空咳、痰の切れが悪いときなど、
喉の深い症状があるときに一役買ってくれます。
もちろんそのまま食べても良いですが、
お水を少し入れてガーっとミキサーにかけてジュースにすると抜群に美味しい!
ハチミツ大根同様、無農薬のレモンを少し絞ると「甘味×酸味」 となってより身体を潤す作用が強くなります。
身体を冷やす作用があるため、冷え性の方はおろし生姜を入れるとバランスがとれます。
秋のおすすめレシピ3
山芋のポタージュ

山芋は、外皮を除いて乾燥させたものが「山薬」という生薬として使用されるほど、パワーの強い食材です。
夏で疲れた胃腸を労わるとともに、肺を補う作用も期待できます。
使うもの
・無農薬の山芋、玉ねぎ
・昆布や椎茸のだし汁
・豆乳または、大豆パウダーを溶いたもの
・オーガニックギー
・無農薬の味噌
山芋と玉ねぎを炒めて、昆布出汁で軽く煮ます。
粗熱が取れたらミキサーにかけて、豆乳を入れ、ギーや味噌、塩コショウで味を調えれば出来上がり。
同じ要領で水分を少なめに作れば、クリームソースとしてドリアなども作れます。
胃腸を休めるための一工夫

さて、「潤す」をキーワードにした
秋に取り入れたいおすすめの食材やレシピをご紹介しましたが
ただ食べればOK!というものでもありません。
初めにも触れましたが
秋は、一年で一番体力を消耗する夏の疲れを癒し、冬に備えて気を蓄える季節です。
夏の疲れをしっかりとリセットさせるためには、
「食べ方」も重要なポイントとなります。
・腹八分目
・温かい食事
・よく噛んで食べる
などの工夫が重要となってきますが、他にも◎朝食か夕食はがっつり食べるのではなく
お粥やスープを取り入れて食べる量を減らす
◎消化を助ける酵素が含まれる発酵食品を取り入れる
といった工夫も効果的です。発酵食品は、動物性のヨーグルトやチーズなどよりも
植物性のものの方が腸まで届くため
ぬか漬けや味噌、納豆などがおすすめ。
こちらの記事で紹介されている、
米の磨ぎ汁に野菜を一晩漬け込んだだけの
水キムチも良いですね。
ぬかみそ漬けの19倍の乳酸菌。効能がすごい!お家で簡単「水キムチ」の作り方。
乳酸菌の量はぬか漬けの18倍!夏バテ防止にも最適な発酵パワー「ひんやり水キムチ」の作り方。
(↑簡単な上に、乳酸菌の量もすごいから本当おすすめ。)
人間だって自然の一部

整った空調に、旬の時期に関係なく手に入る食材
太陽が沈んだ後でもまぶしさを感じるほどの明るさ。
そんな便利になりすぎた毎日を生きていると、ついつい忘れてしまいがちですが
人間だって自然の一部であることに変わりありません。
東洋医学の基本理論で「天人合一」というものがありますが、これは
「天(自然)と人はもともと一つのものである」
という考えです。私の場合ですが、不思議なもので、体調が悪かったときには季節や自然を感じるとることを忘れがちだったように思います。
食事や、生活を改め、健康的な生活を送るようになった今は
季節の変化や自然のあり方を肌で感じることができるようになり、「自分も自然の一部なんだなー」を心地よく感じられるようになりました。
私の場合は、今になってようやく、その当たり前で大切なことに気が付きました。
夏は夏らしく、秋は秋らしく生きる。
季節を、自然を感じて生きることで、より健やかになることができるはずです。人間も自然の一部であるということは、間違いのない事実なのですから。
皆様のより健康でより楽しい毎日のお役に立てますように。
IN YOUおすすめのマヌカハニーや風邪対策グッズを使ってみよう!
 【人気の非加熱マヌカハニーがパワーアップ!】今までで最高値の抗菌性MG500+になって再登場今すぐここをクリック!
【人気の非加熱マヌカハニーがパワーアップ!】今までで最高値の抗菌性MG500+になって再登場今すぐここをクリック!
おすすめの記事
「本当にいいもの」は一般市場に出回っていないワケ。有機栽培の現実と、オーガニック後進国日本の課題。秋は栄養を蓄えて冬眠に入る季節。無理は冬に響きます。秋に起こる「乾燥」や「冷え」から生じる不調と対策方法。
所要時間3分!常備したいお助け調味料、抜群に美味しい「味噌ふりかけ」の作り方。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)