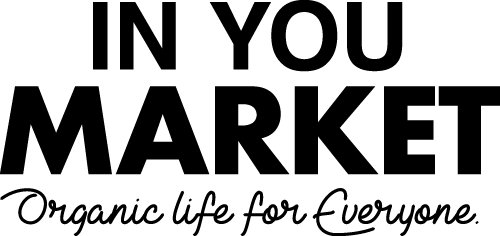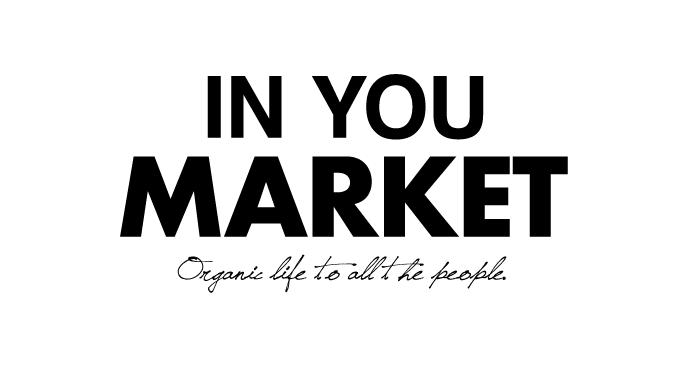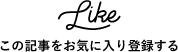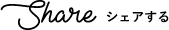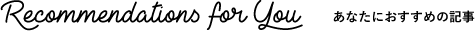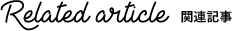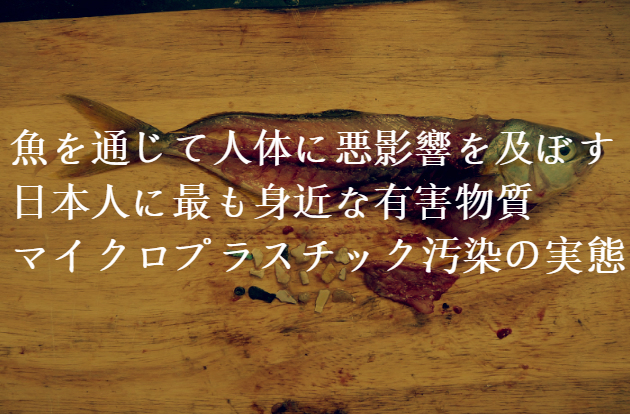幸せを叶える6つの「自己肯定感」とは?|子供の自己肯定感を育てるために親が実践すべき、たった一つのこと

幸せをかなえる6つの「自己肯定感」とは?
子供の自己肯定感を育てるために親が実践すべき、
たった一つのこと
「自己肯定感」
このキーワードが気になるお母さんやお父さんは
多いのではないでしょうか?
“日本の若者の自己肯定感の低さは諸外国と比べても低水準。”
様々なメディアでこのような記事を目にした方は、
「我が子は本当に大丈夫だろうか」
「日本社会の仕組みが悪いのではないだろうか」
そんな漠然とした不安を持ち、
「ポジティブな言葉がけをしよう」
「子供の自己肯定感を高めるように、
あの本に書いてあったことを実践してみよう」
もしくは、
「どうしたら、子供の自己肯定感は高くなるのだろうか」
「そもそも、私も自分に自信なんてないし・・・」
と思っている方も多くいらっしゃると思います。
そこでこの記事では、そもそも
「“自己肯定感”とは何なのか」ということ
そして、自己肯定感を高めるために、
お母さんに実践して欲しいことを紹介したいと思います。
人生の成功と幸せは自己肯定感が作る!

予防医学指導士の私がカウンセリングをしていると、
「人の目が気になります」
「いつも不安なんです」
「私は自己肯定感が低いと思います」
という、クライアント様は多くいらっしゃいます。
予防医学指導士の仕事はカラダとココロを整えて、
本当の健康へ導くお手伝いをすること。
カラダの栄養は食べ物から。
そして、
ココロの栄養は自己肯定感から。
カウンセリングを続けていくうえで、
ココロの栄養は自己肯定感が鍵、
だということがわかってきました。
そしてカラダとココロ、両方の栄養が満たされてこそ、
真の健康体という、本質的な意味での成功と幸せは実現します。
実は、かつての私は自己肯定感がとても低く、
自分のことは嫌いだし、自信もないし。
すぐになんでも諦めてしまう性格でした。
でも、気がづけば、
「私って、けっこういい感じじゃない?」
と、思うように少しずつ変わってきたのです。
クライアントの皆様の自己肯定感をどうやったら上げられるのか。
我が子である息子達の自己肯定感も気になる・・・。
そこで、「自己肯定感について改めてしっかり学ぼう!」と
先日、自己肯定感カウンセリングの講座を受講してきました。
今回は、そこで教えて頂いたことを皆様にシェアしつつ、
私の経験も交えてお伝えしていきます。
「自己肯定感とは何か」を
きちんと説明できますか?

今回受けた講座で私が一番衝撃を受けたのは、
自己肯定感の高い人でも、常にポジティブでいるわけではない
ということ。
人間は常に良いことばかりでもないし、
落ち込むこともあります。
当たり前の事なんですが、これまで私は、
「自己肯定感が高い人というのは、ポジティブに物事を
捉えられ、ネガティブな感情を抱くことが少ない人のこと」
だと思い込んでいたのです。
だから、私自身、頑張ってプラス思考になろう!
と意識をしていました。
しかし、それだけでは不十分だったのです。
自己肯定感は6つに分類される
自己肯定感は6つの要素に分けられることを、皆さんはご存知でしょうか。
そして、そのそれぞれの分野を意識して高めていくことが、
「自己肯定感を高くする」ことだと言えるのです。
ざっくり「自己肯定感を上げよう」と言うと、
何から始めたらよいのかよくわかりませんが、
6つの要素を一つずつ整えて行こうと思うと、
その道筋が見え、やるべきことが明確になると思います。
ここからはそれぞれの要素と、その高め方のヒントについて
順にご紹介していきましょう。
<1>自己肯定感の「根」~自分には価値がある

自己肯定感が高い人といえば、まずは
「自分自身を無条件で価値がある人間だと思える人」だと
捉えている方が多いのではないでしょうか。
自己肯定感の大元の根源ともいえる、
「自尊感情」がこれに当たります。
自分の個性や人柄を自分で評価して、
「なかなかいい性格だよね」「いい所がいっぱいあるよね」
と、思える気持ちのことです。
この自尊感情が低ければ
「私なんて、ここにいる意味がないし」などと
学校や職場などのグループや組織に属していることが辛くなりますし、
「私なんて、生きている意味ないし」
と、生きている事が自体辛くなってしまいます。
そして、日本の若者はこの自尊感情が弱いため、
諸外国よりも自殺率が高くなっているといいます。
なぜ、日本の若者が自尊感情を抱きにくいかといえば、
日本の社会が、何かにつけて自分を他人と比べてしまいやすい構造をしているため。
他人と比較して自分をダメなんだと思い込んだり、
自分を否定されたと感じる言葉がココロに残り、
「また、否定されてしまう」と思って行動が出来なくなったり。
その積み重ねがさらに自己肯定感をどんどん下げていきます。
そして潜在意識に残る過去の経験がまた自己肯定感が高低を
決定づけていきます。
子育てにおいて、この潜在意識がいかに大切かを知りたいかたは
こちらの記事をぜひご覧ください。
「ほら、やっぱりね」と人間は思いたい。潜在意識の扉が閉まる6歳までに母親が子育てで気をつけること。これを知れば子育てが変わり、あなたの人生も変わります。
<2>自己肯定感の「幹」~ありのままの自分を受け入れる

ありのままの自分を受け入れることを「自己受容感」と言います。
子供の頃に、〇✖を頻繁に下されるような環境におかれていると、
人は自分で自分に対しても、〇✖の判断を下しやすくなります。
しかも自分の行動だけでなく、
自身の思考にまで、〇✖を下すようになるのです。
例えば、
ネガティブな感情を持つのは✖
あの人を嫌いと思うのは✖
掃除するのがめんどくさいと思うのは✖
嬉しい感情を表現するのは✖
こんなことで満足しては✖
という具合です。
いかがでしょうか?
あなたの頭の中には、このような自分の思考に対しての
たくさんの✖で一杯ではありませんか?
私は、自分自身を内観していくことが真の健康に
繋がっていると考えています。
でも、この内観をした時にこそ、つい自分に✖を出してしまいがちなんです。
逆に、〇を出そうと頑張るとしんどいですよね。
私は、「ありのままの自分にOKをださなくては」
と思っていましたが、いつも空回りしてばかりでした。
自己肯定感が低い人が、自分に〇を出すのは難しいと思います。
なぜなら、自分に〇を出せないことに対して、さらにまた責めてしまう
という悪循環にハマってしまうからです。
そこで、私は自分に〇を無理には出すのを、ある時からやめました。
〇を出せる時はそのままにしておきます。
✖を出しそうな時は、
「や~めた!!」と思考をストップさせます。
私達は一日6万もの思考が頭に現れてくると言われています。
そしてそのうち、8割がネガティブ思考です。
つい悪い事を考えてしまうのが人間の性なのです。
なぜなら、それが危険な環境から身を守る術だったのです。
そのようなネガティブな危機予測によって人間は生き延びてきました。
逆に、「どうにかなるさ~」と、明るく前向きに生きていたら、
人間は絶滅していたかもしれません。
ネガティブな思考が出てきたら。
「人間らしいな私(笑)」と、クスッと笑いに変えられるくらいに
なりたいものです。
<3>自己肯定感の「枝」~失敗は成功の基

3つ目の要素は「自己効力感」です。
この自己効力感が低いと「自分はダメだから・・・」と
すぐに諦めてしまう大人に育ちます。
そして、すぐに逃げてしまう自分に落ち込み、
行動を起こさないから結果も出ずに、さらに落ち込む。
そんな負のスパイラルに陥ります。
失敗は成功の基。失敗を失敗と思わず、やり続ける事が人生の成功哲学ですが、
自己肯定感の根っこである、自尊感情と
幹である自己受容感が低いと、この自己効力感も低くなりがちです。
ただ、この自己効力感は、小さな目標を掲げ、達成を積み重ねていくことで、
高くなっていきます。
自己肯定感が低い人の中には、目標設定が高過ぎる人が多いように感じます。
逆に出来ているのに出来ていない。と思っている方も多くいらっしゃいます。
つまり、自分の現状を正確に把握できていないのです。
私も目標を大きく持ってしまいがちです。
大きな目標を掲げるのは良いことですが、
その目標と自分の差にまた落ち込んでしまっては本末転倒です。
例えば、以前、私が朝活をしようと思った時、
「早朝3時に起きよう!!」と目標を設定したことがありました。
そして、時間通りに起きられない自分はダメだと思いました。
そこで今では午前4時半~5時に起きています。
目標設定を変えて、寝る時間や夕食の食事の量や質を変えることで、
朝起きる時間がこの時間に定着しました。
このような小さな成功体験の積み重ねによって、
「自分は目標設定とやり方を間違えなければ出来るんだ」
と自信がついていきます。
私の場合は、起きる目標時間があまり早過ぎることに気づき、
寝る時間を早くしたり、早く寝るために子供の寝かしつけなどを工夫したり、
良い睡眠が取れるように夕食の質や量を気をつけたり、
日常の小さなことを変えることで、目標は達成できるのだと自信がつきました。
<4>自己肯定感の「葉」~根拠のない自信

自分に自信がない。
自分のやっていることが合っているのか不安。
そんなクライアント様の言葉をよく耳にします。
例えば「私の食事法はあっているのかどうか不安」というご相談が
多くあります。
そこで4つ目の自己肯定感「自己信頼感」が強ければ、
「私が選んだ食事法なんだから、きっとこの食事で健康になる!」
と、思えるのですが、すぐには結果は出てこないのが食事法ですので、
とたんに不安になってしまう方が多いのです。
しかし根拠のない自信を持つことが、スピード感のある行動へ繋がります。
「自分を信じて行動し続けること」
もし、違った時にはすぐに方向転換する勇気。
そんな自分の直感を信頼する力が自己信頼感です。
<5>自己肯定感の「花」~自分の道は自分が決める

5つ目の自己肯定感は「自己決定感」です。
自分で決めたことは成功しても失敗しても、悔いはありません。
自分の人生を自分の意思でコントロールしているという感覚こそが重要です。
継ぎたくもない家業を継ぐ。
これは分かりやすく、自分が選んだ道ではありませんが、
これよりも、もっと自己肯定感が低くなるケースがあります。
これは「無意識」に親の願っているであろう進路を、
子供が(無意識的に)忖度して、進む場合です。
しかも本人は自分の願った道だと信じています。
「実家を離れたら、親が寂しがるかな」
「親はきっと公務員になって欲しいはず」
そんな子供の優しさからくる勝手な思い込みから、
自分の進むべき道が変わっていき、
自分で決定した人生だけど、
なんとな~く不満。
なんとな~くやっていることがしっくりこない。
でも、人生なんてこんなもんなのかな。
という自己肯定感が低い状態になっていくのです。
人生という大きな選択だけでなく、
自分で選んだ服。
自分で選んだ本。
自分で選んだ外食のメニュー。
「自分で選ぶ」という経験を積み重ねることが、
自己肯定感の高さに繋がります。
もし自分で決定することが怖かったり自信がなければ、
憧れのあの人なら、どんな答えを出すのかな?
と、考えるのがおススメです。
そして、最近私が特に意識していることがあります。
それは「ダラダラすることを自分で決める」ということ。
疲れた時、やる気が出ない時、そんな時は
「やらないといけない・・・」「動けない自分はダメだ」と、
思いがちですが、
「今は自分の意思でダラダラしている」と、
自分の言葉に出します。
そうすると、「自分がダラダラすることを決めた」と、
自己決定感は高まります。
自分はダメ人間だと後ろ向きにならずに済むのでおススメです。
<6>自己肯定感の「実」~役に立っている自信

最後の自己肯定感は「自己有用感」です。
人間の最大の喜びは誰かの役に立っていると感じることです。
「相手を喜ばせること」が出来るのは、
とても人間らしい行動で、
喜んでいる人を見て、giveしたこちらも、
嬉しい気持ちになるのは、人間の特権です。
ハーバード大学が75年以上にわたって700人以上を対象に
「幸福」に関する研究を行った結果
「幸福度が高い人は人間関係が良好」という結果が出ているそうです。
人と繋がる事で、人は充実感を得ることができます。
人と繋がる事で、人のお役に立てる機会が増えます。
自己肯定感が高い子供を育てるために
親が実践すべき、たった一つのこと

ここまでご紹介してきた
自己肯定感の6つの要素はそれぞれ人によってバランスが違います。
「自己決定感」は強いけど「自己有用感」が低い人。
「自尊感情」だけ極端に低いが、他はそこそこ高い人。
人それぞれです。
自分の強みと弱みを知っておくことが大切です。
では、まだまだ未知数の子供の自己肯定感を高くするためには、
一体何をどのようにやっていけばいいのでしょうか。
「やれば出来る!!」と励ますことでしょうか。
それとも、子供の言うこと、やること全てにOKを出すことでしょうか。
人間関係を良好にするために、積極的に人と関わる環境を用意することでしょうか。
自己肯定感を高くする方法はたくさん世の中に溢れています。
何を選択するのかは、親自身ですが、
その前に、一つ親である皆さんに知って欲しいことがあります。
自己肯定感の高い、ある人物のことです。
有名なスポーツ選手
大企業の創設者
歴史を動かしたあの人
でもなく・・・
その人物とは・・・
実は、あなたのお子さんです。

そう。実は、子供は生まれながらにして既に自己肯定感が高いのです。
自己肯定感が高いからこそ、自分を信じて、たとえ何度転んでも、
諦めずに歩く練習をするのです。
「わたしなんて歩けるわけないわ・・・もう歩くのなんてや〜めた」
なんていう、赤ちゃんはいないですよね。
ですから、「子供の自肯定感を高くする」は正しくなく、
「自己肯定感を低くさせない」ことこそが重要なのです。
生まれつき高い、子供の自己肯定感を
下げないために親が心がけたいこと
子供の自己肯定感を高いまま維持するには、環境が何よりも大切です。人間は「代理強化」が強い生き物です。
つまり、直接教えられるよりも、見て、感じて学習する生物なのです。
徒弟制度などは教えられるよりも、
師匠の背中を見て仕事を覚えるという世界ですよね。
実は、子育てにおいても、口で教えるよりも
背中を見せて子供に伝わることの方が断然多いのです。
つまり、子供の高い自己肯定感を維持したまま、
子供を成長させるには、親が自己肯定感が高い状態でいることがとても大切です。
親であるあなた自身が自己肯定感を高めれば、
子供の自己肯定感は高いまま維持できる
「でも、自己肯定感の低い私が、果たして子供の手本になれるだろうか」と心配な方はぜひご安心ください。
一度低くなってしまった自己肯定感は、何歳からでも高くなります。
先にご紹介した「根」「幹」「枝」「葉」「花」「実」の
6つの分野、それぞれに自己肯定感を上げるヒントがあります。
「自分はこの分野が高いな。ここは低いけど、意識したら上げられそう!」
そんな風に自分を客観視して、ぜひ、行動を起こしてください。
自己肯定感を上げる事は、日々の小さなことの積み重ねなのです。
子供の自己肯定感をどうにかしよう心配する前に、
親であるあなた自身があなたらしく、
キラキラ輝く姿を子供に見せてあげて下さい。
自己肯定感の高い親の姿を見て、
お子さんは大人になることが必ず楽しみになるはずです。
自分を好きでいることが当たり前になります。
「自己肯定感なんて高くて当たり前でしょ?」と
幸せな大人へとスクスクと成長していくことでしょう。
参考文献:『自己肯定感の教科書 中島輝(SB Creative)』
オーガニック食品やコスメをお得に買えるオーガニックストアIN YOU Market
IN YOU Market子供に食べさせたい! IN YOU Marketのオーガニックフード

IN YOUプロデュース!
ほんもの小麦のビスケット/キャロブビスケット【選べる2種2袋セット】|全原料農薬不使用!小麦の概念が覆される、食べても眠くならないし肌荒れもしない体に優しいおやつ
¥ 1,794 (税込)こちらの記事もおすすめです!
私を救った育児のヒント「モンテッソーリ」。気づかないうちに子供の可能性をつみ取っていませんか?腸内環境は3歳で決まる!|今すぐに始めたい、子供の簡単・腸活習慣
日本で子どものうつ病が急増?根本原因とオーガニックな解決のヒント

この記事が気に入ったら
いいね!しよう



_Market-Slider.jpg)